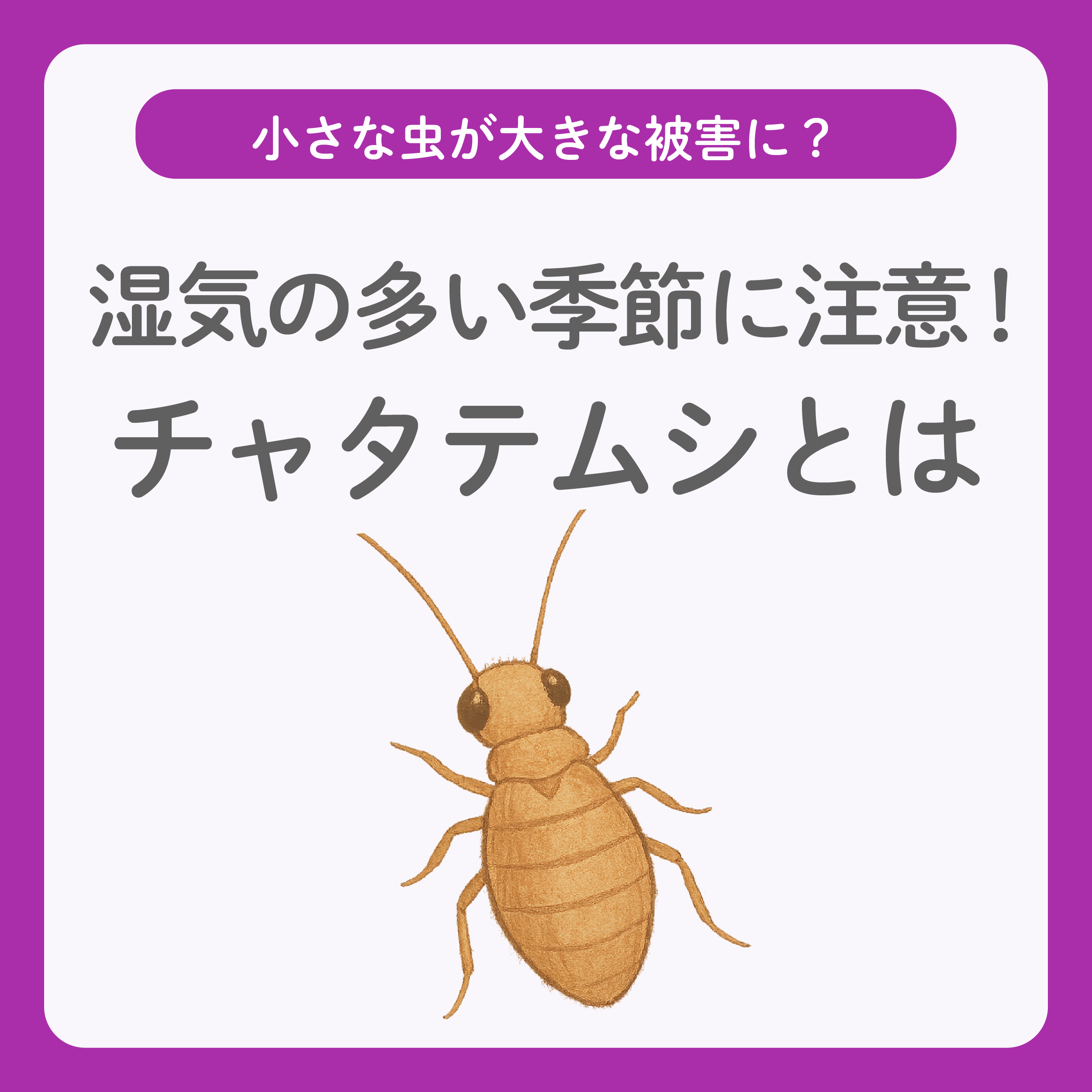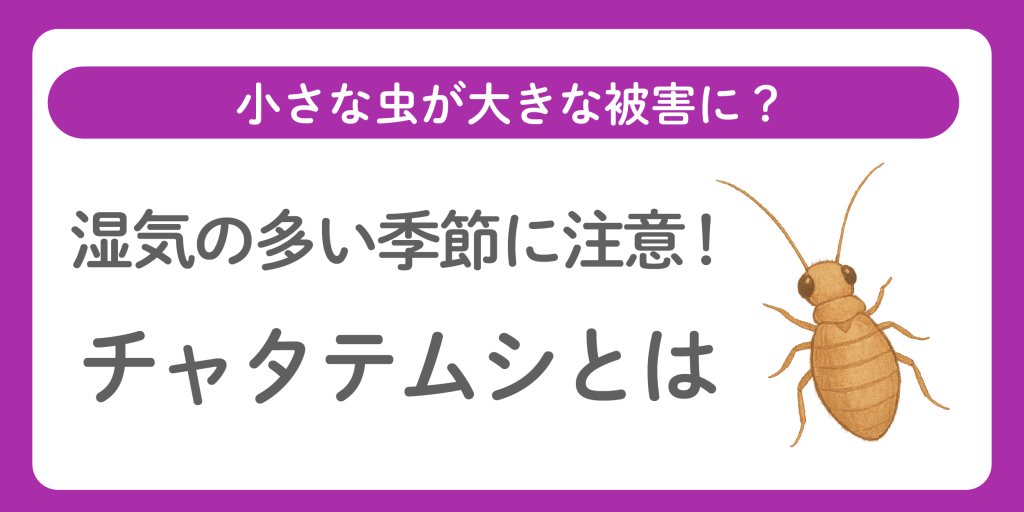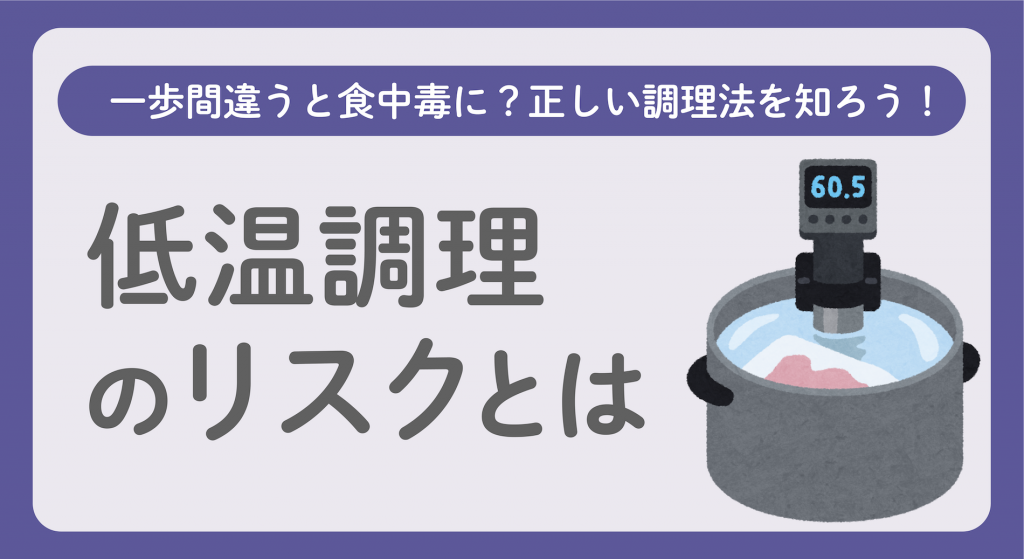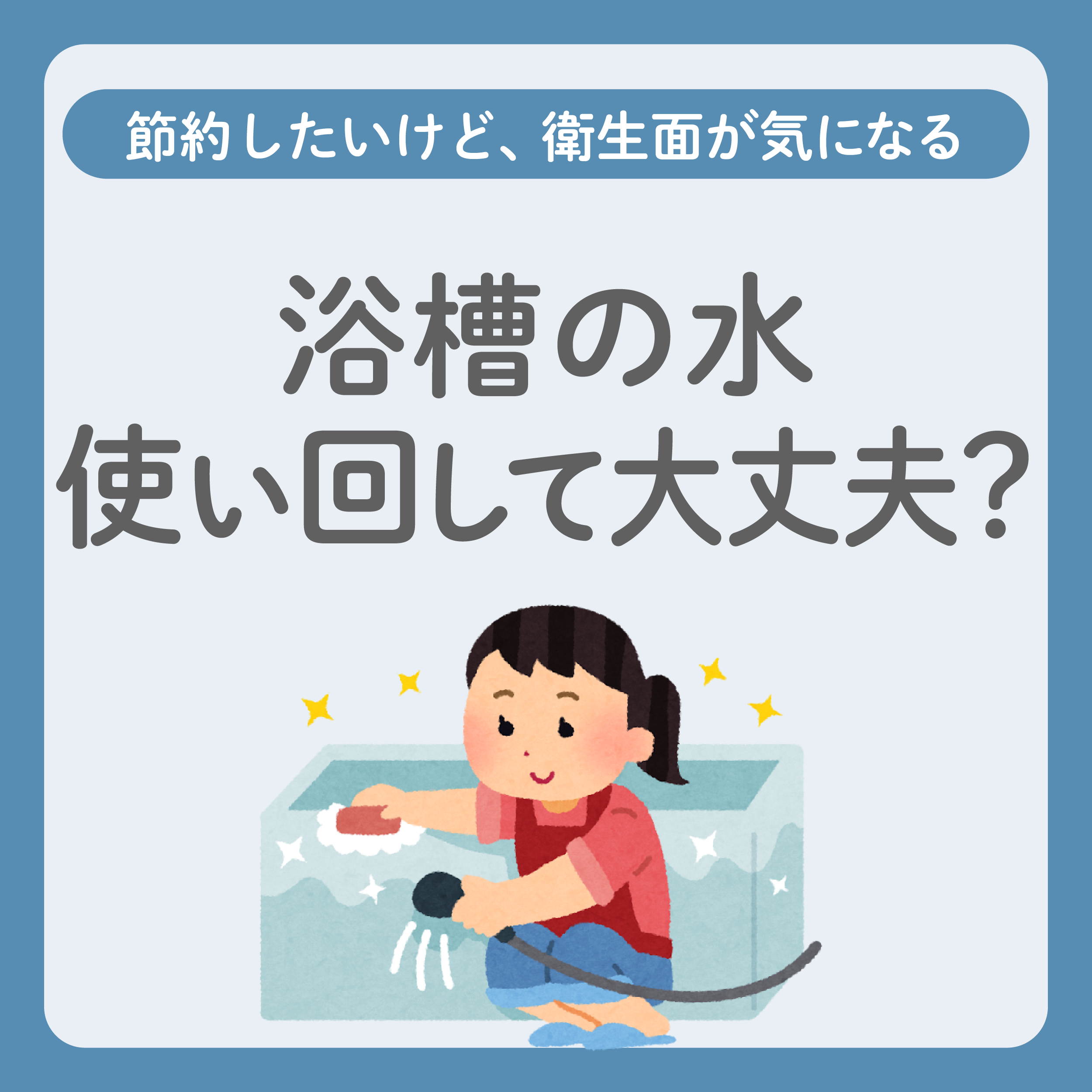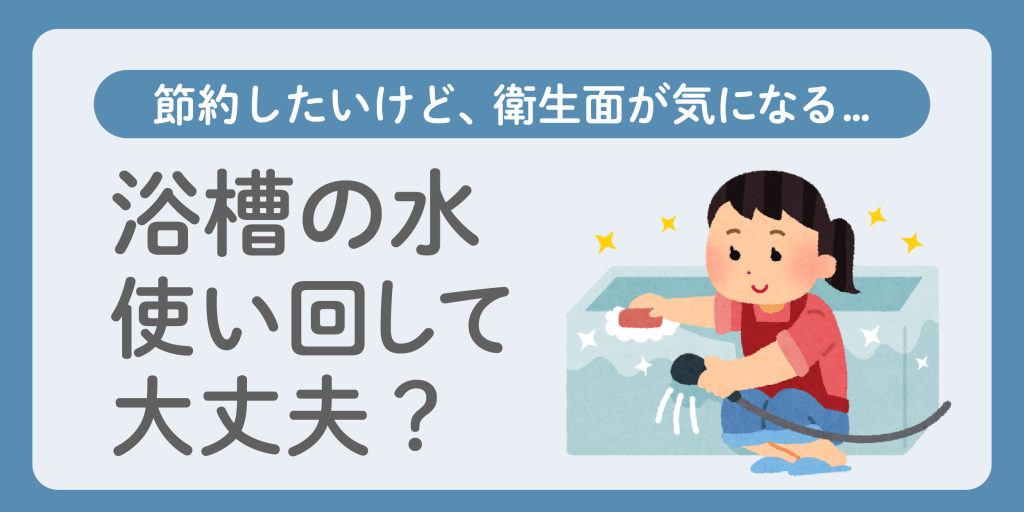夏は「細菌」による食中毒に要注意!
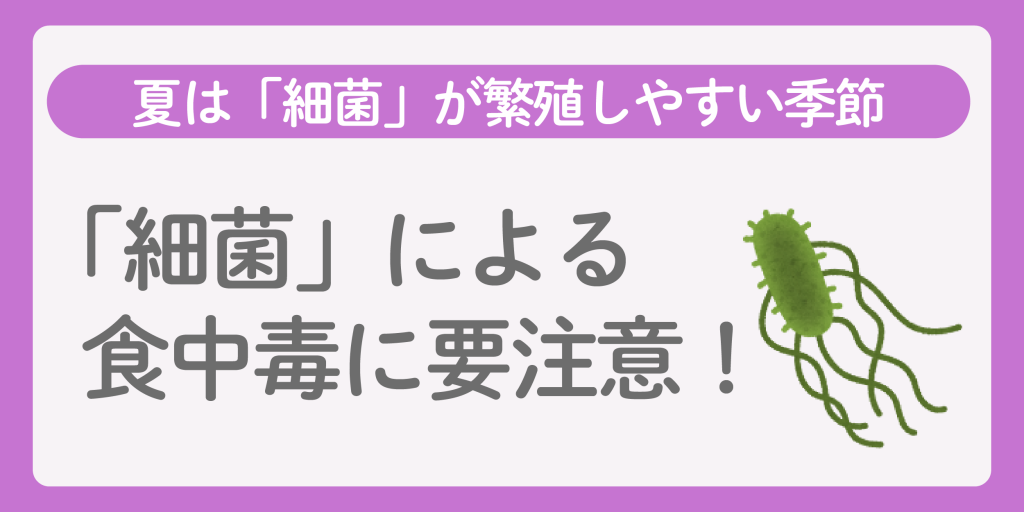
食中毒の原因は年間を通じてさまざまですが、特に夏は細菌が原因となるケースが多くなります。
鶏肉や卵、生野菜、加熱が不十分な料理などは細菌が増殖しやすく、お弁当や作り置きの管理には注意が必要です。
代表的な細菌と主な原因食品は以下の通りです:
• サルモネラ(肉・卵)
• カンピロバクター(鶏肉)
• 腸管出血性大腸菌 O-157など(加熱不足の肉や野菜)
• 黄色ブドウ球菌(手指の傷から)
• セレウス菌(パスタ・チャーハンなどの穀類)
• ウェルシュ菌(カレーや煮物を長時間放置)
これらの中には、少量の毒素でも環境次第で重篤な症状を引き起こすものもあります。
〈手洗いは“丁寧に2回”がおすすめ〉
手洗いは食中毒予防の基本です。
「10秒×2回」の手洗いを行うことで、時間をかけた1回の手洗いと比べて、ウイルス量を1/10〜1/100にまで減らすことができるとされています。
調理前の手洗いでは、以下の点を意識しましょう。
• 指1本ずつを包むように洗う
• 手首や親指、指の間、爪の間までしっかり洗う
• 洗った後は合掌のように手を合わせて水を切る
• 手指を乾燥させてから、アルコール消毒を行うとより安心
特に生肉・生魚を扱った後は、こまめな手洗いを心がけましょう。
〈お弁当づくりで気をつけたいポイント〉
夏場のお弁当は「水分」が細菌増殖の原因になります。以下の工夫が安全につながります。
• 水分の多い煮物などは避ける
• 熱いまま容器に詰めず、冷ましてから入れる
• 保冷剤を活用し、保存温度に注意する
• 仕切りには大葉やバランなど、水気の少ないものを使う
〈食中毒の症状が出たらすぐに医療機関へ〉
下痢、嘔吐、発熱などの症状が現れた場合は、自己判断せず、すぐに医療機関を受診しましょう。
特に下痢止めの安易な使用は避け、こまめな水分補給が大切です。
また、食べたものの内容や、外食時のレシート、症状の経過などを記録しておくと、診断時に役立ちます。