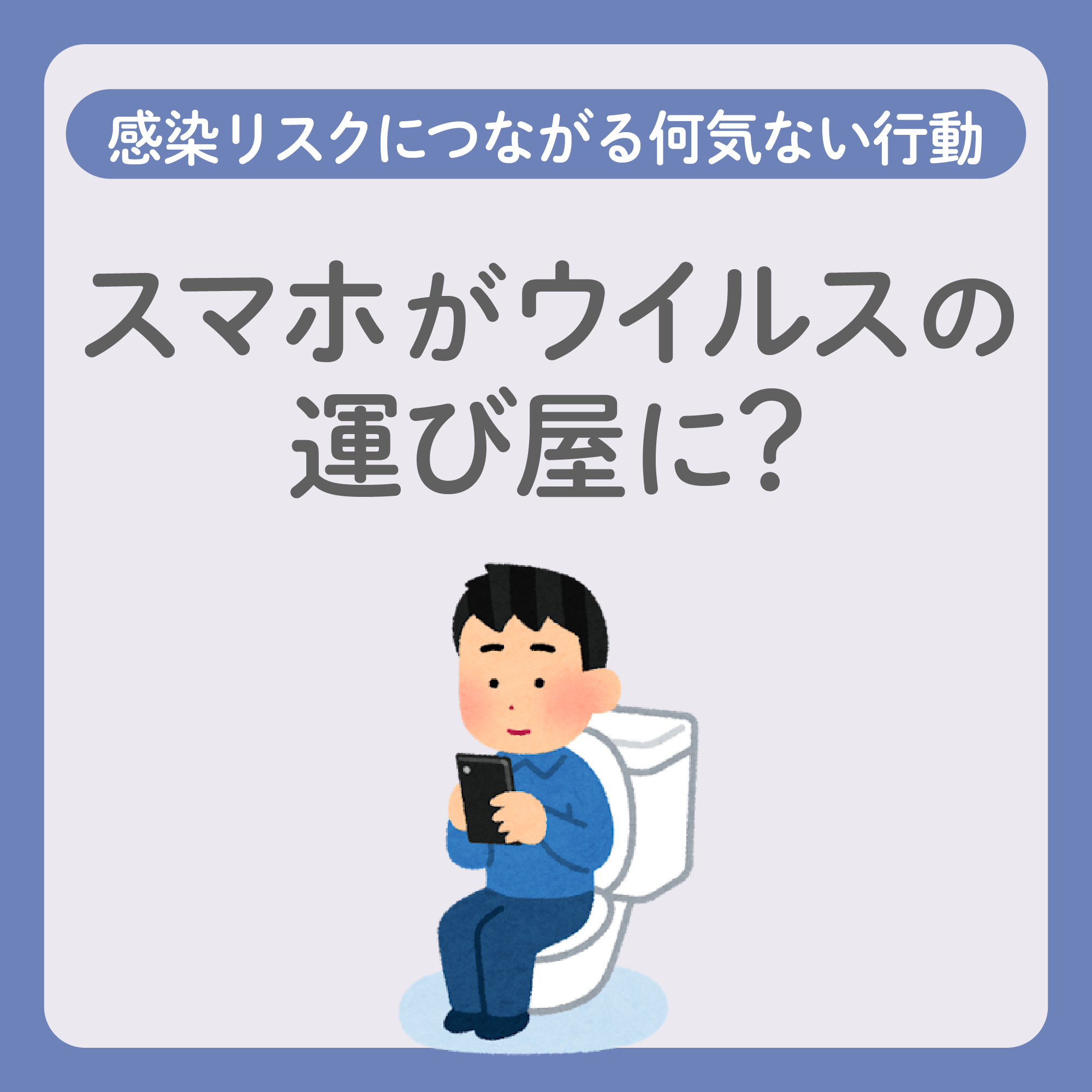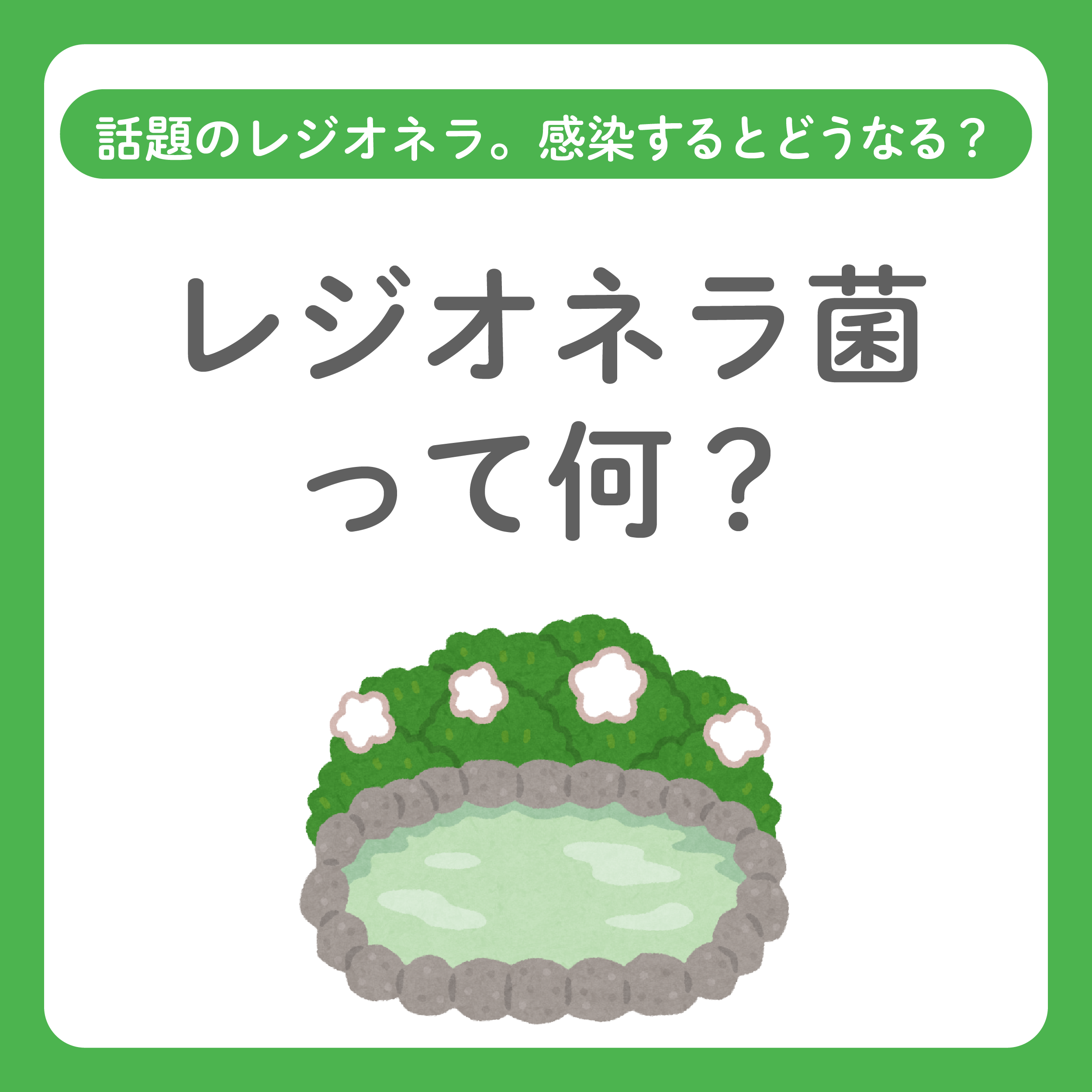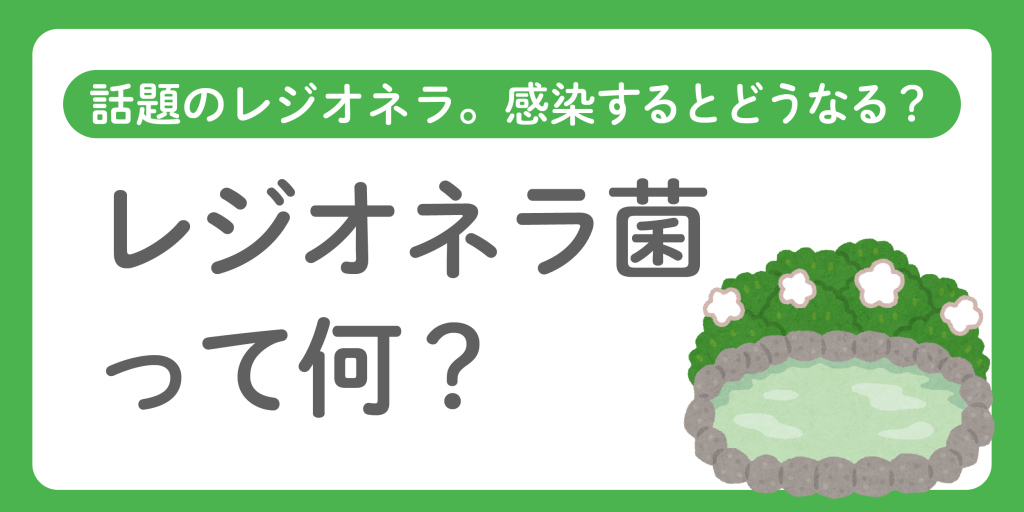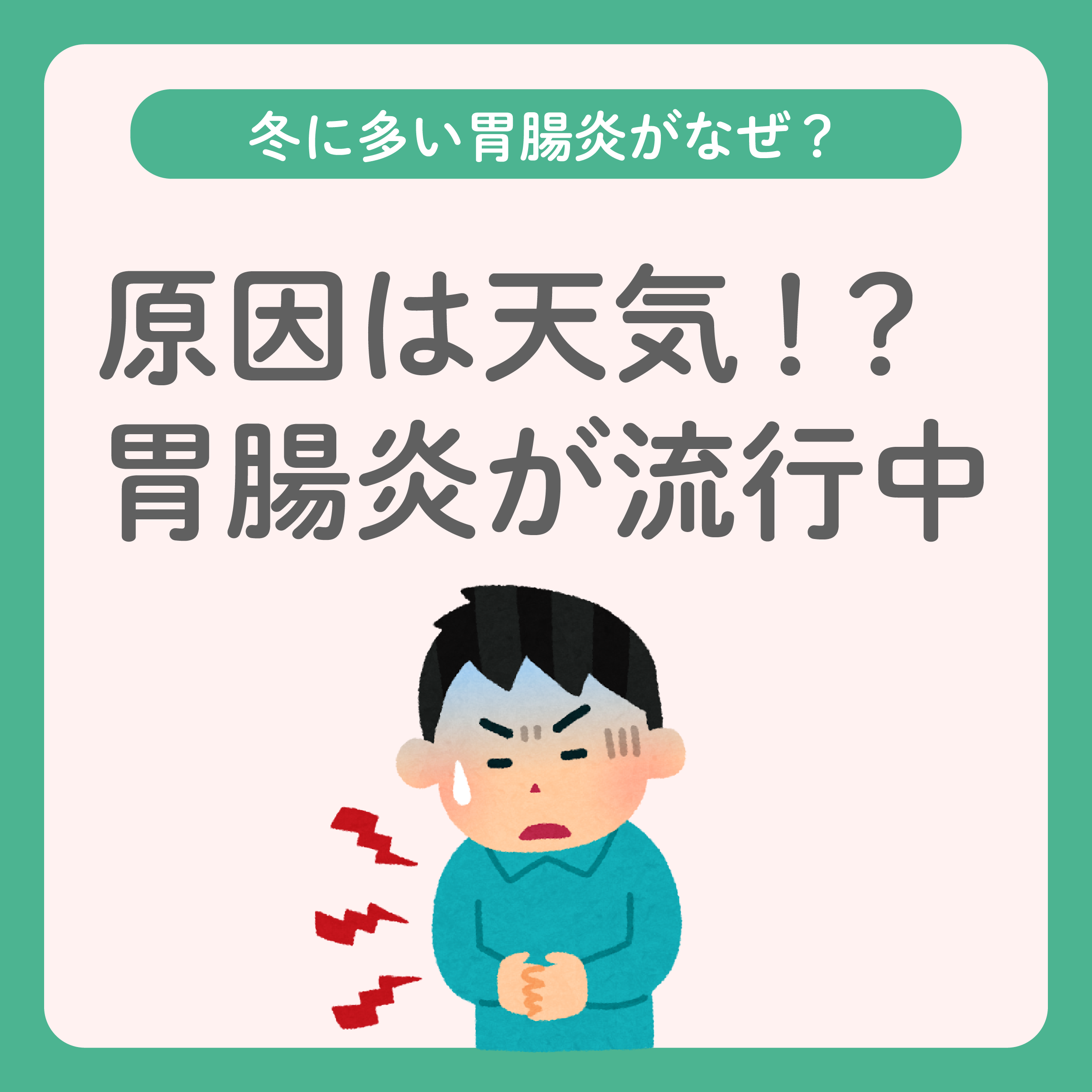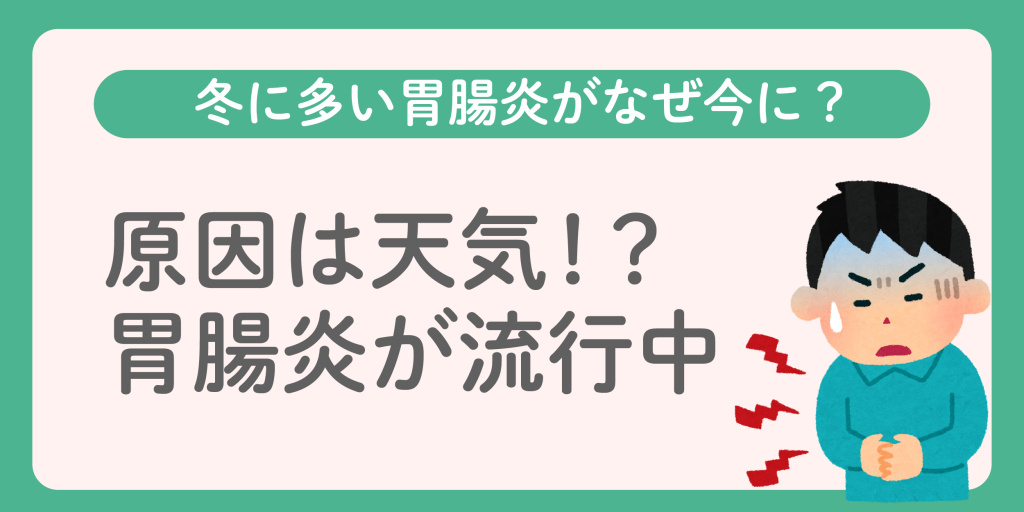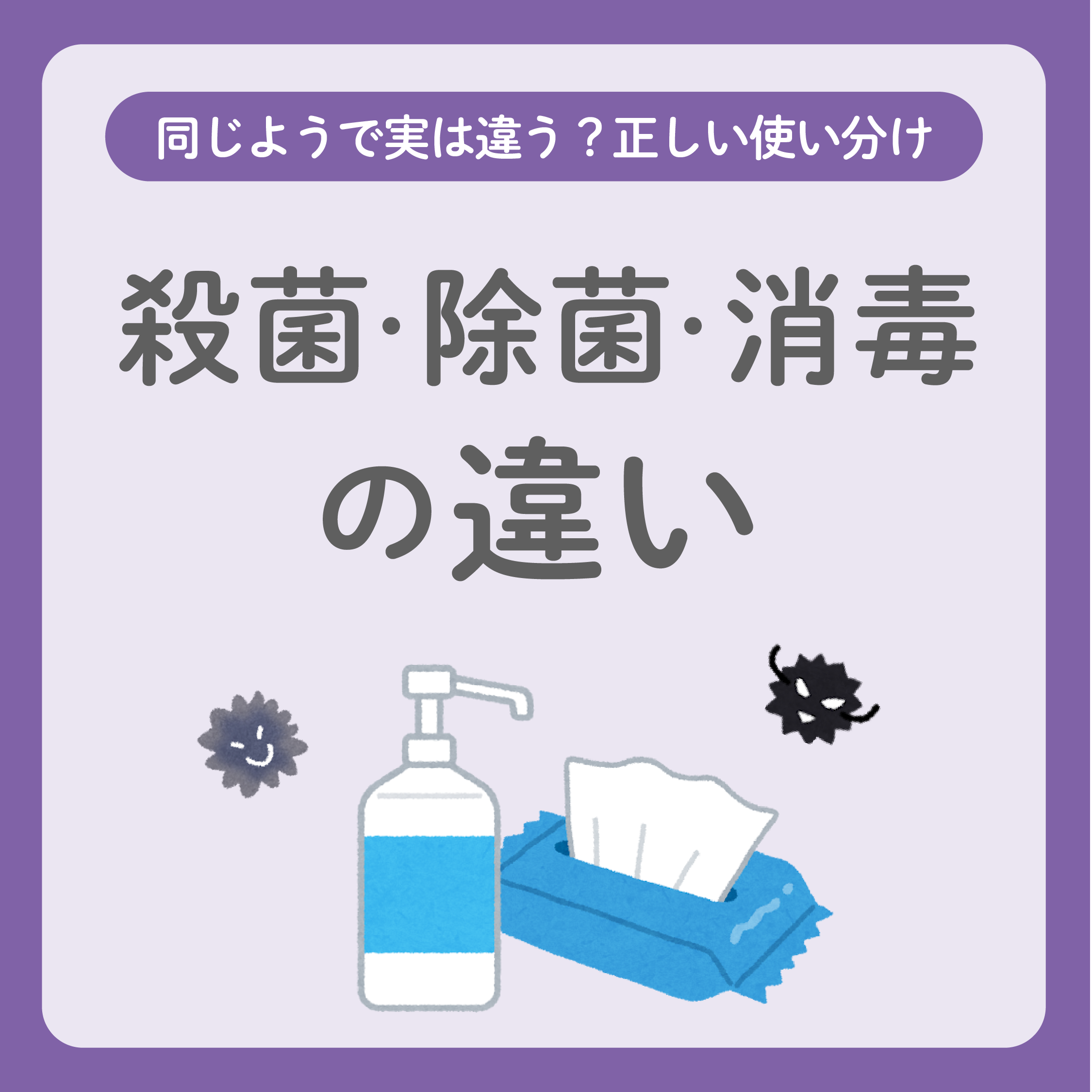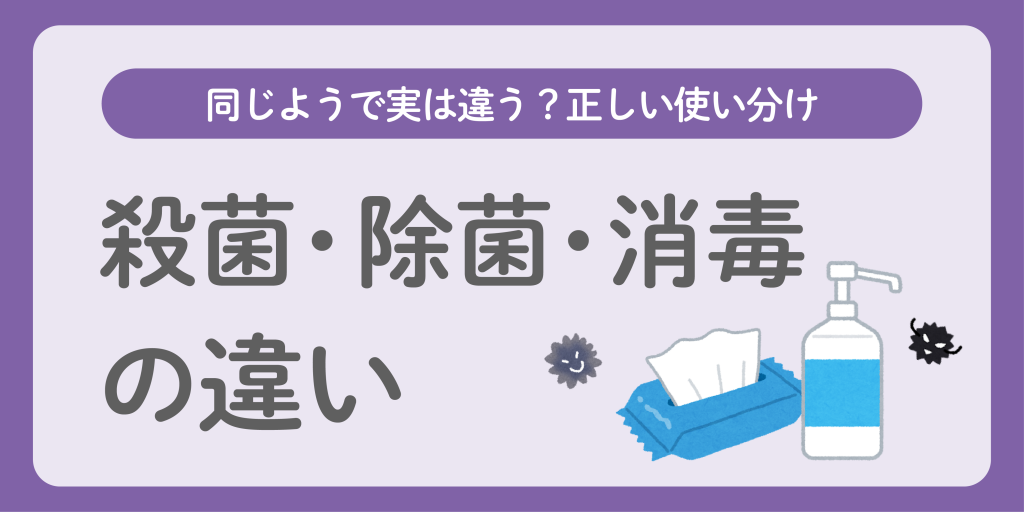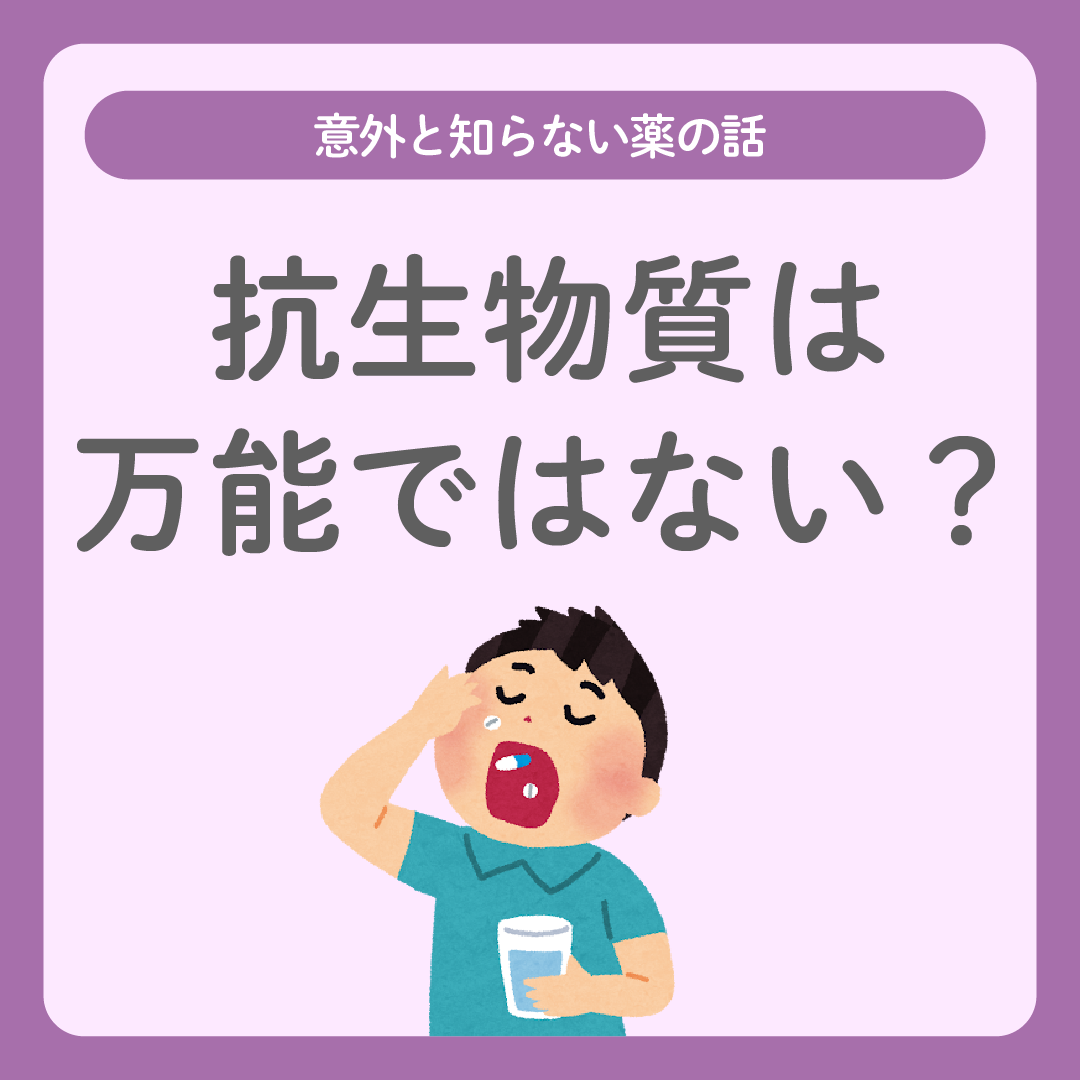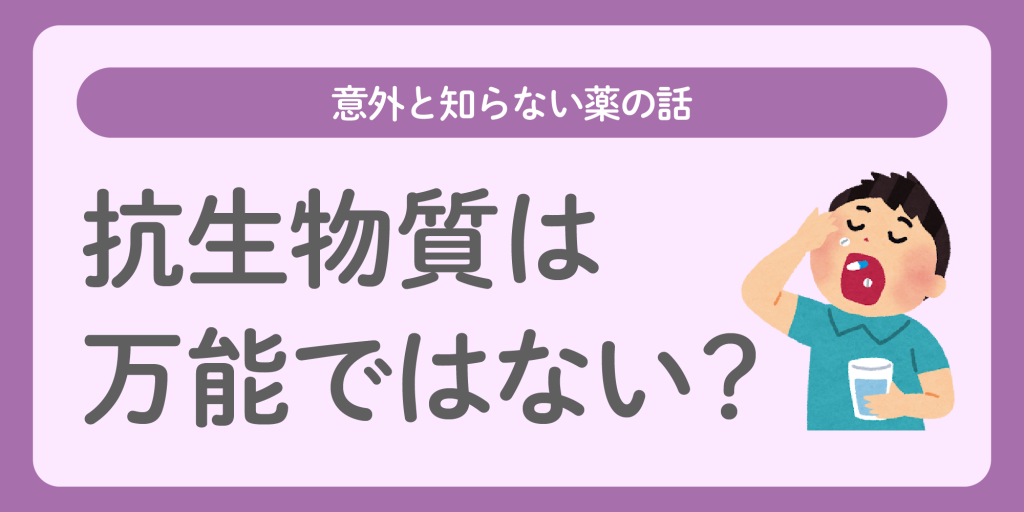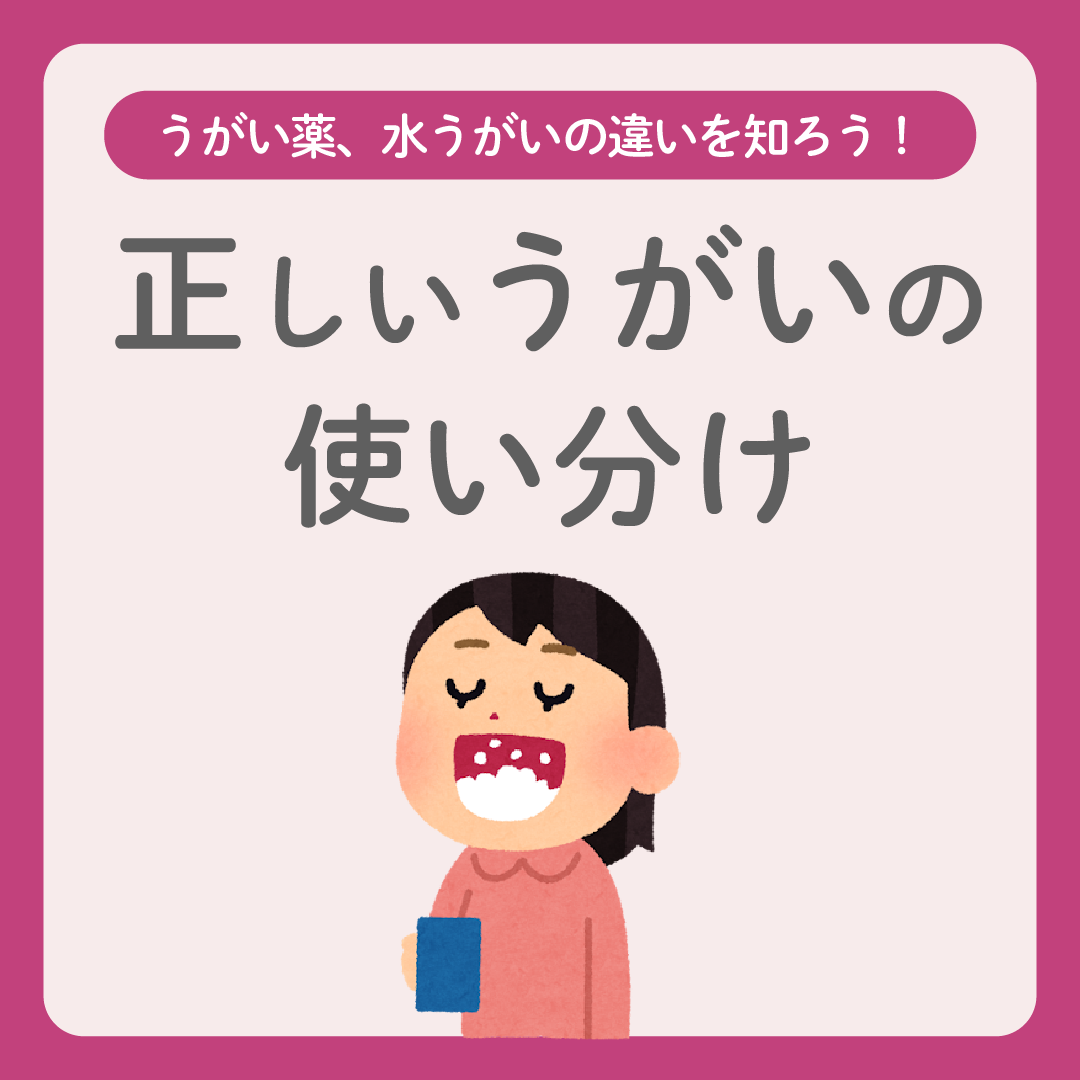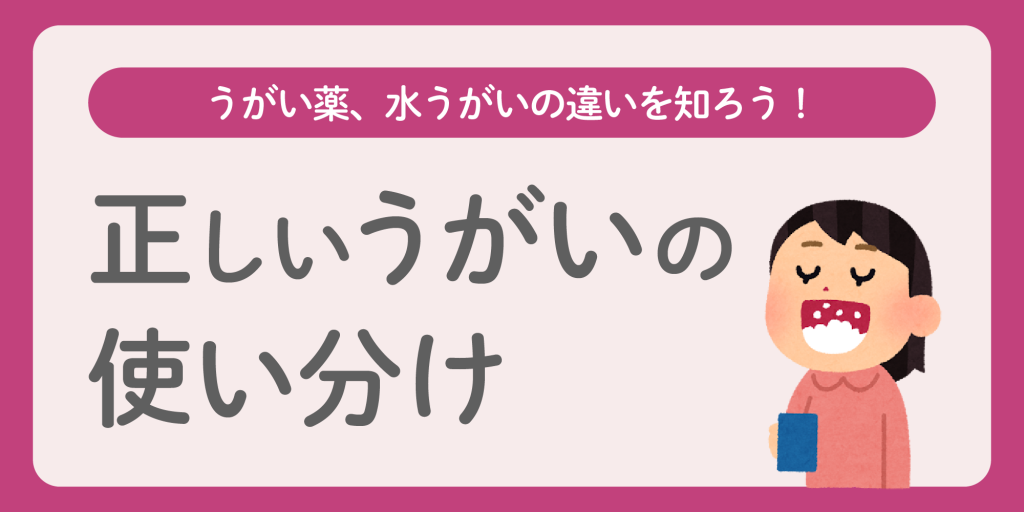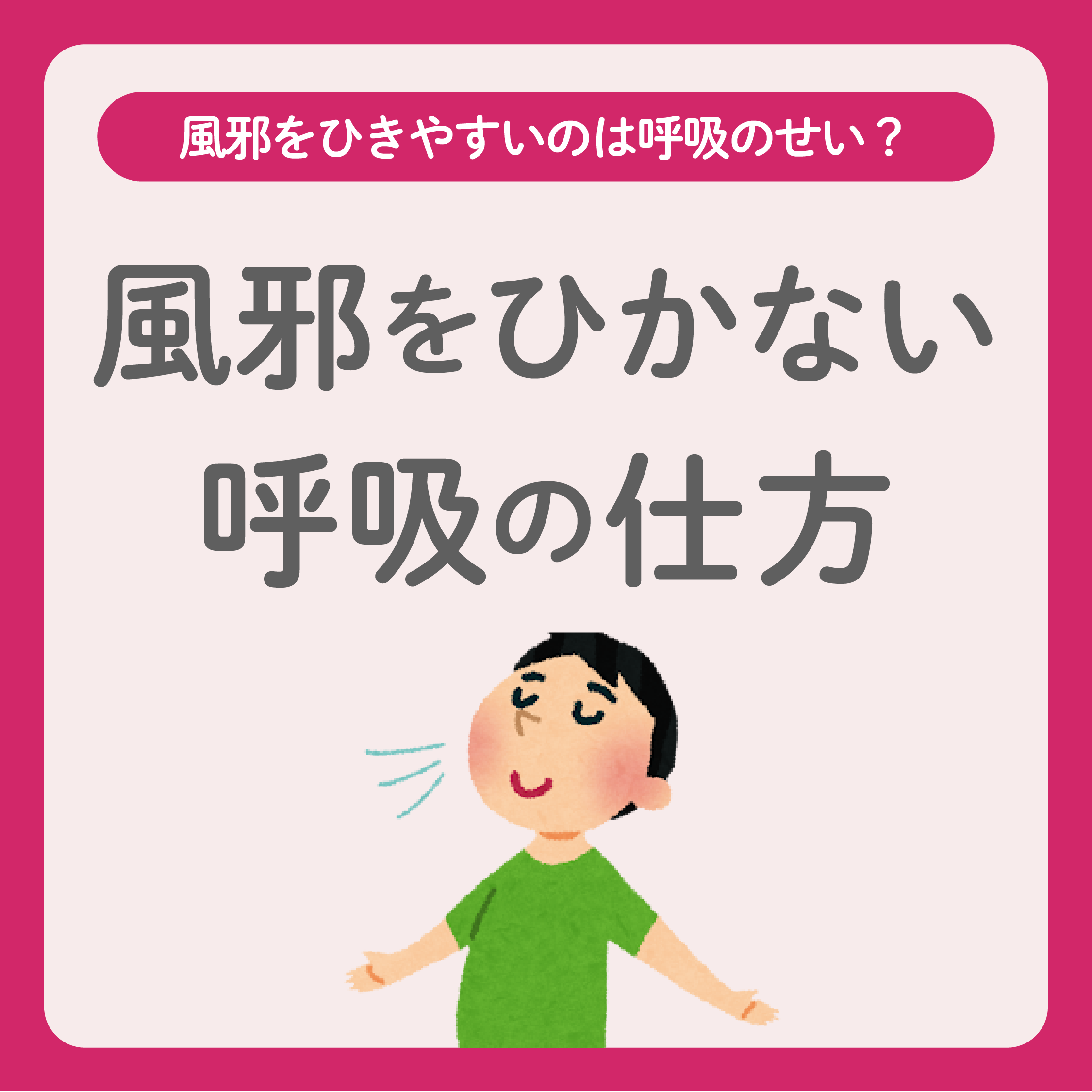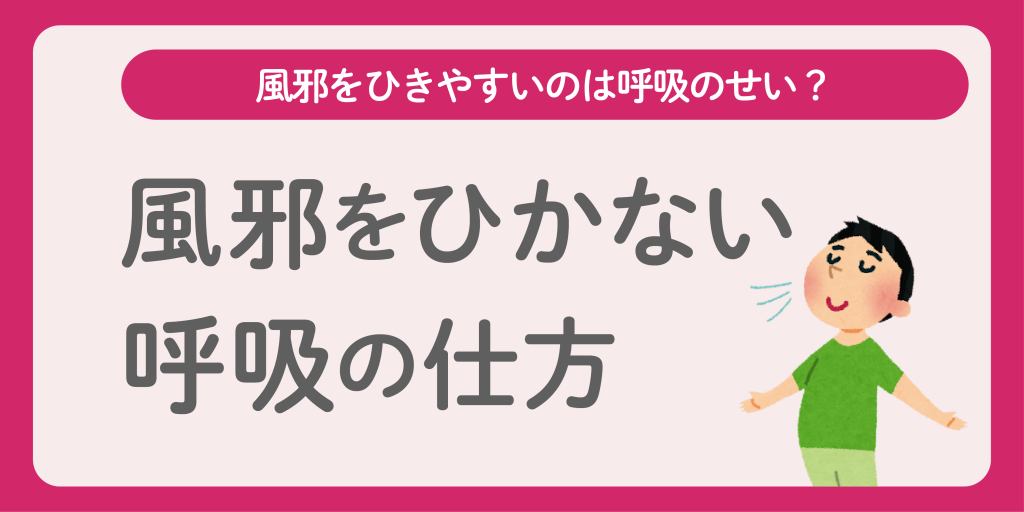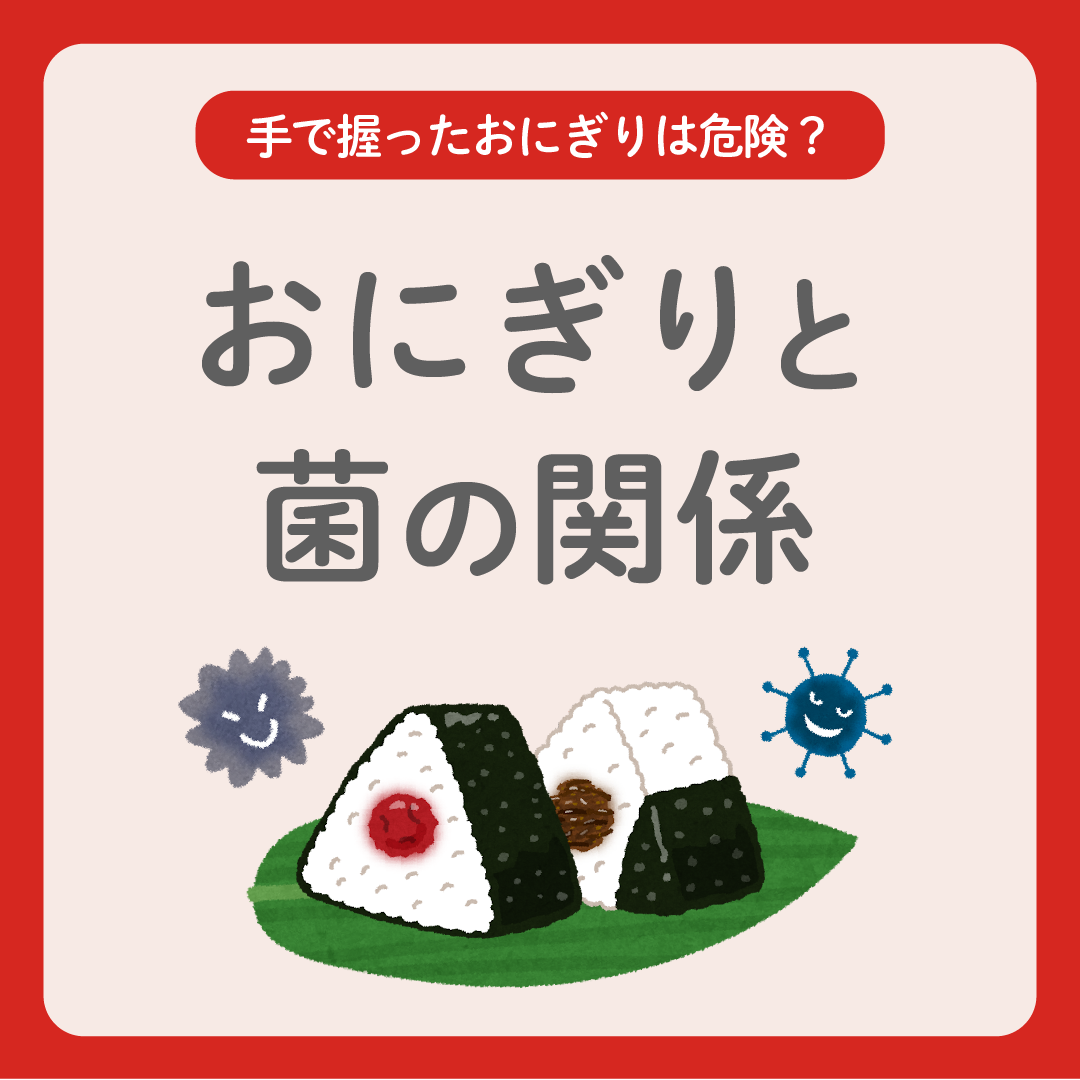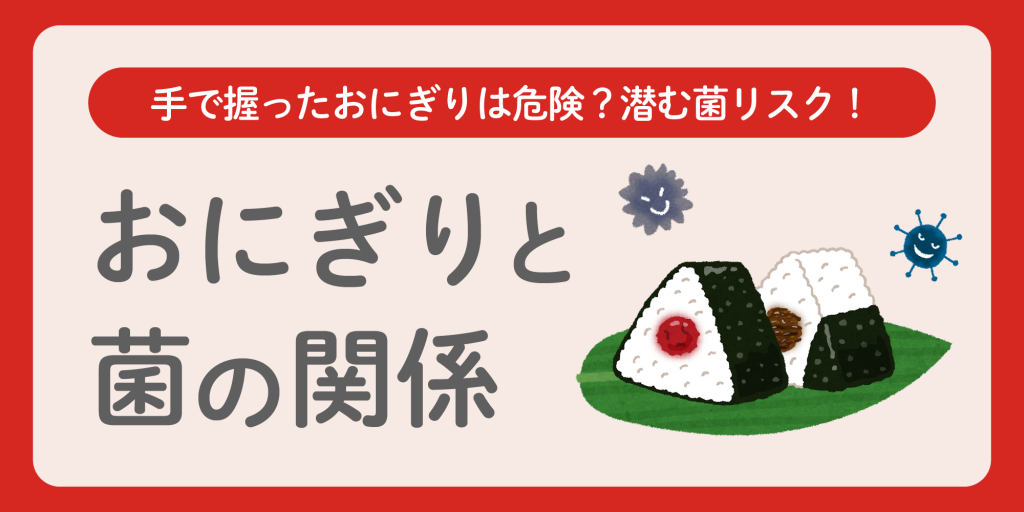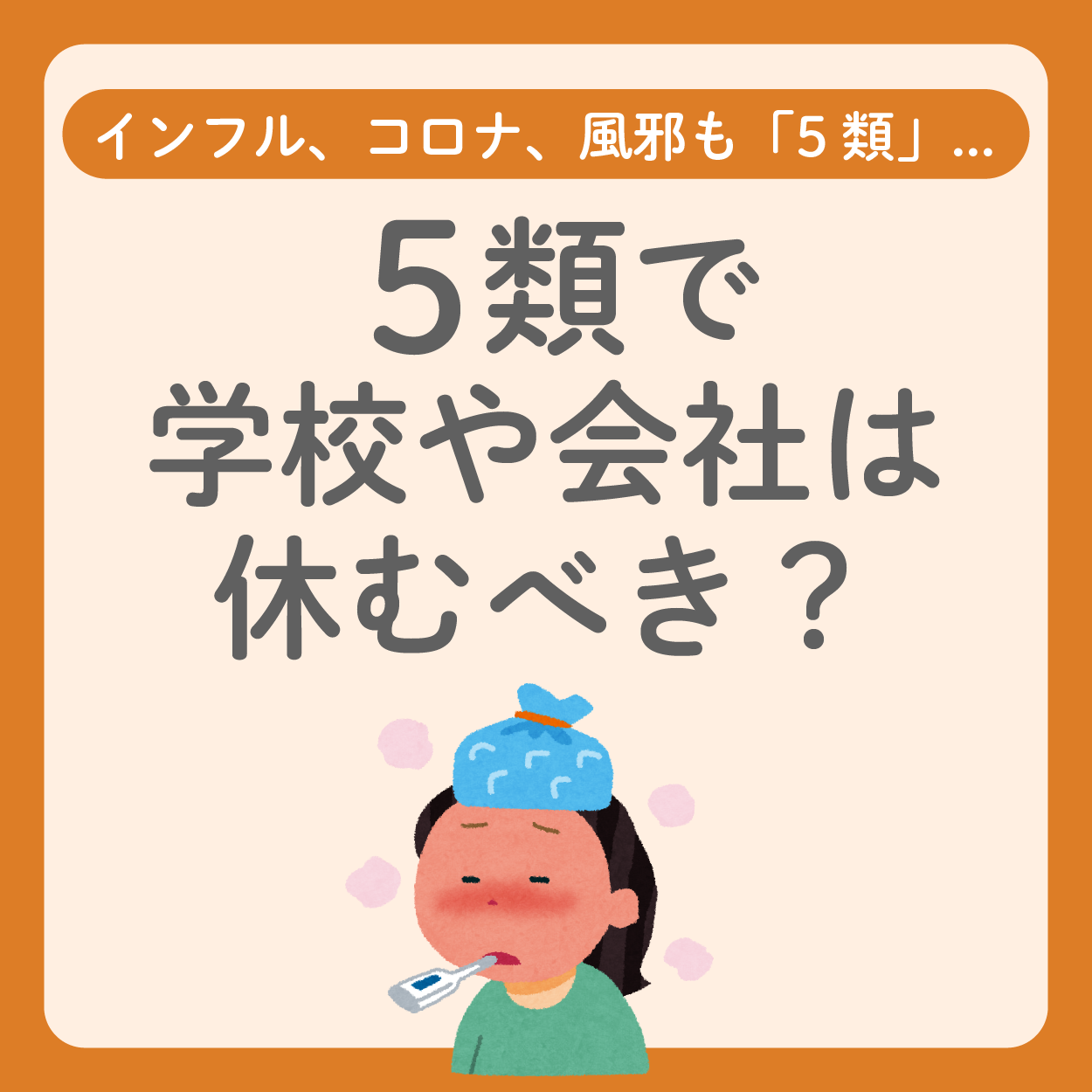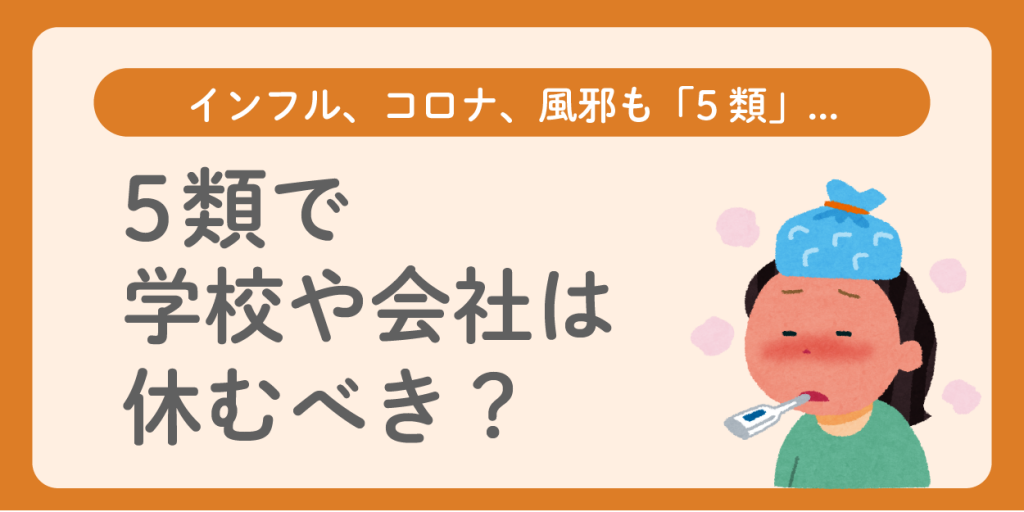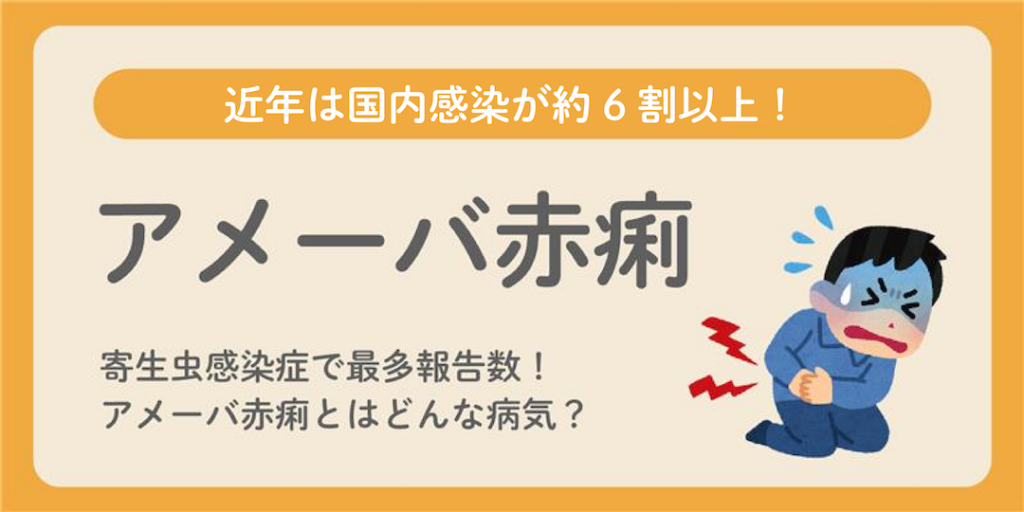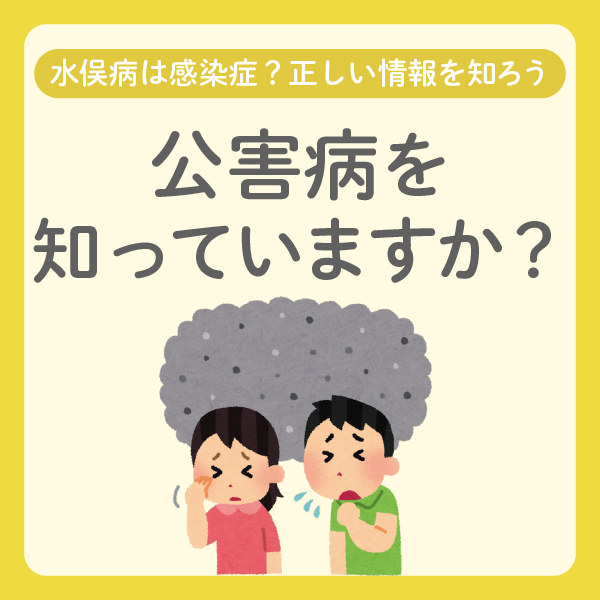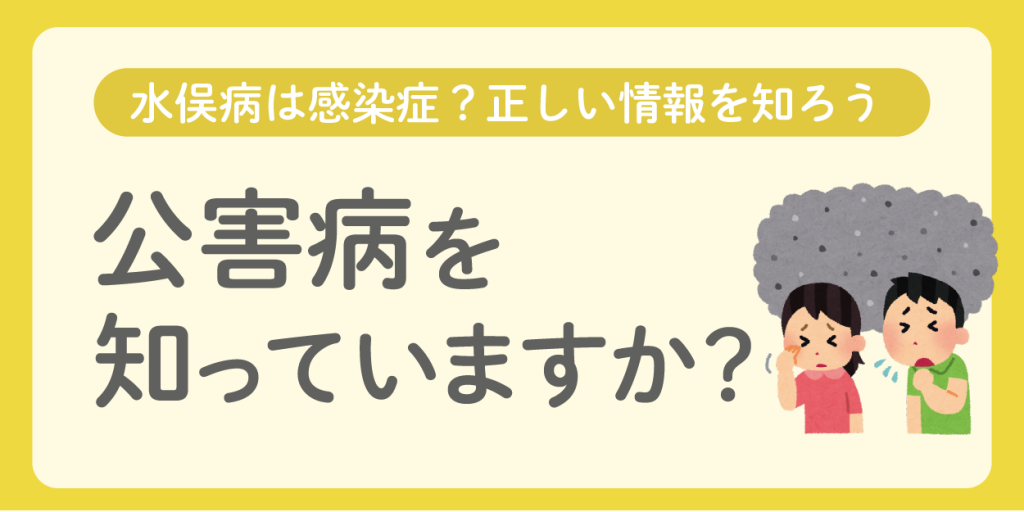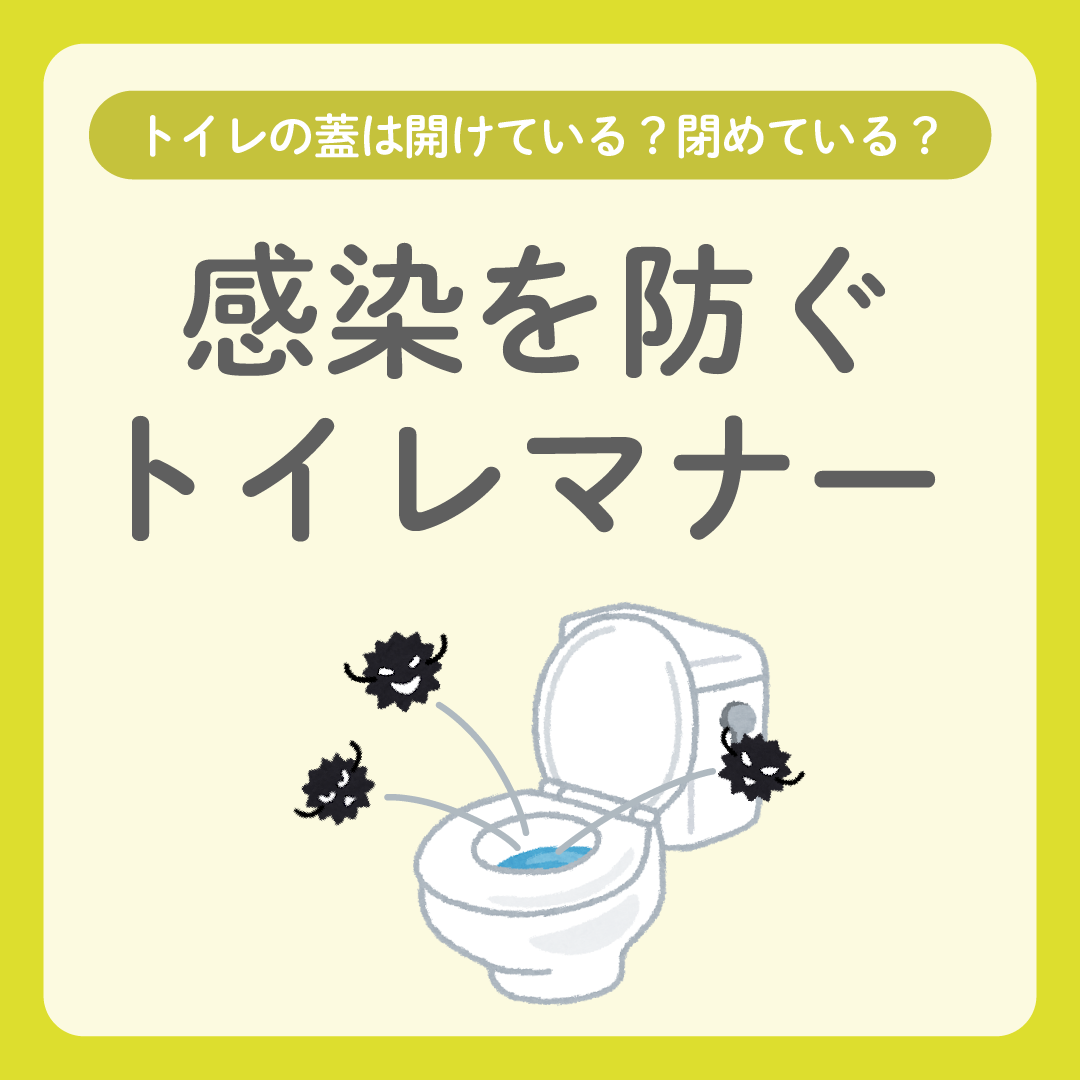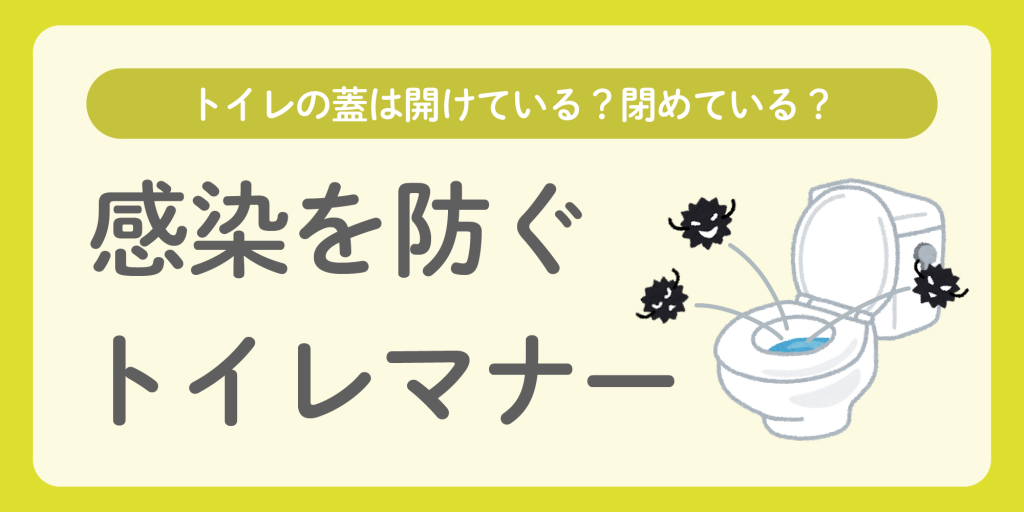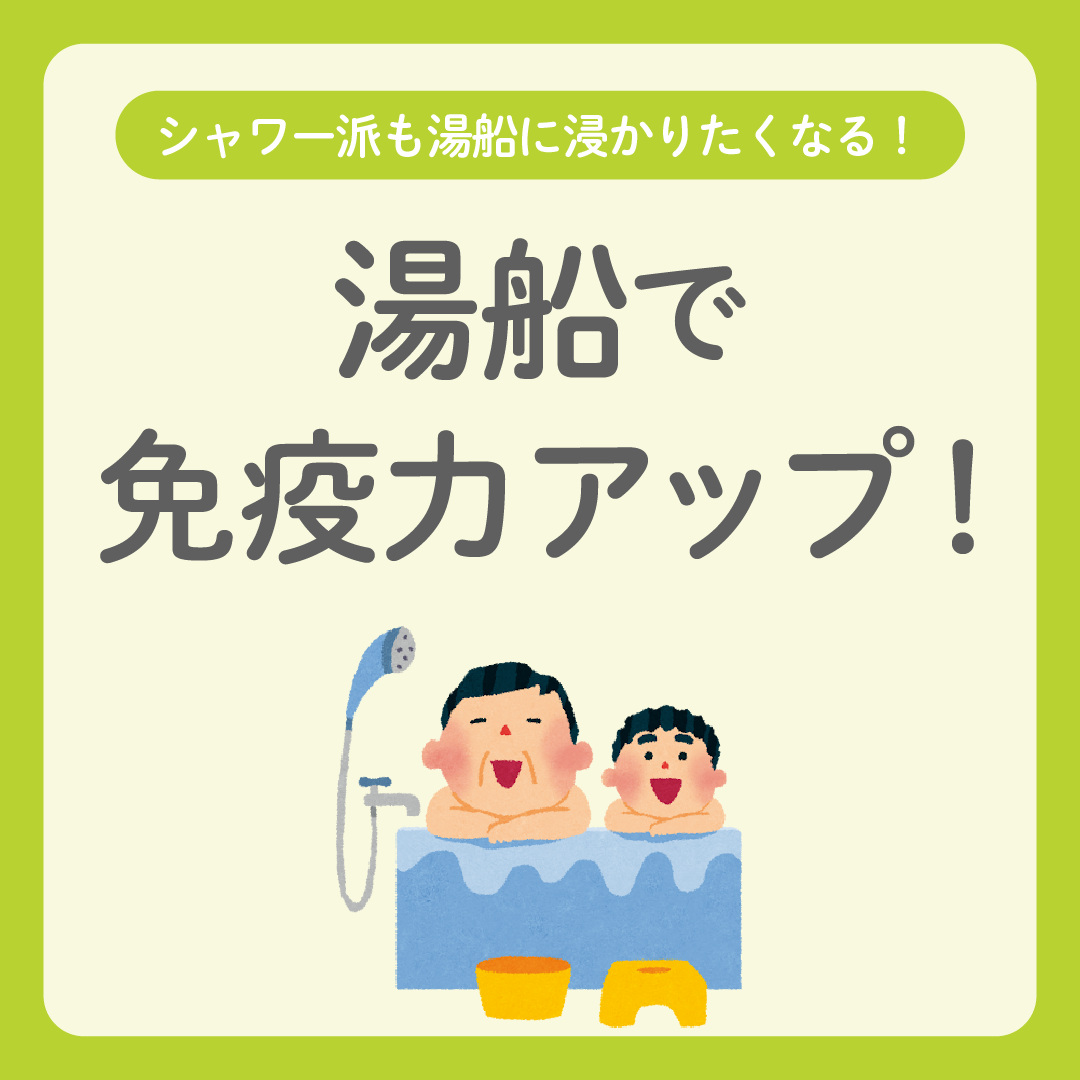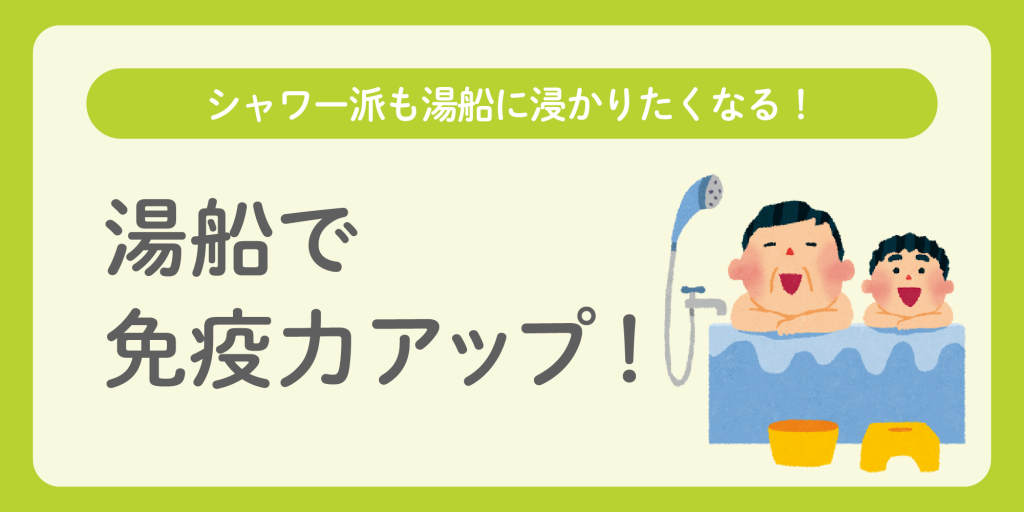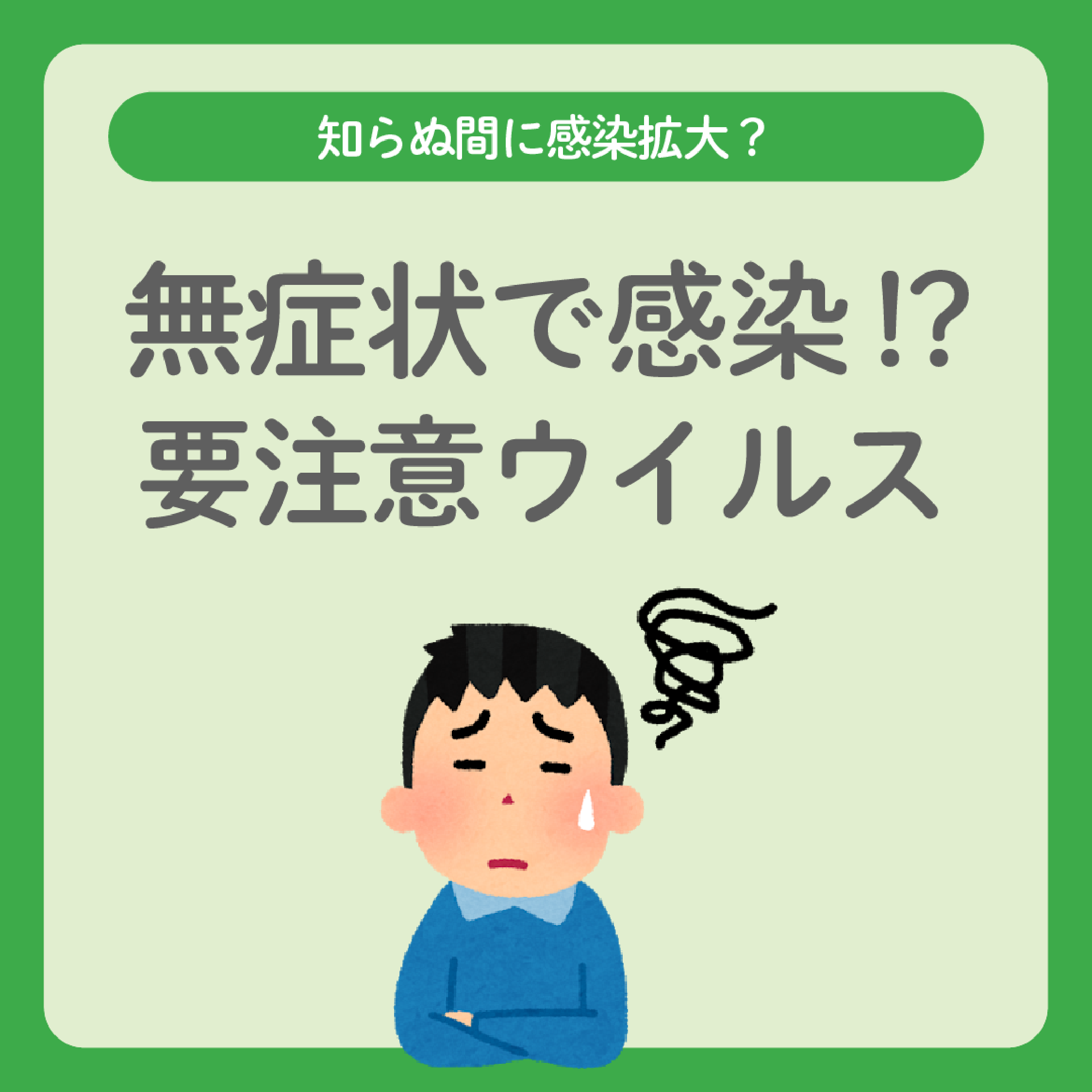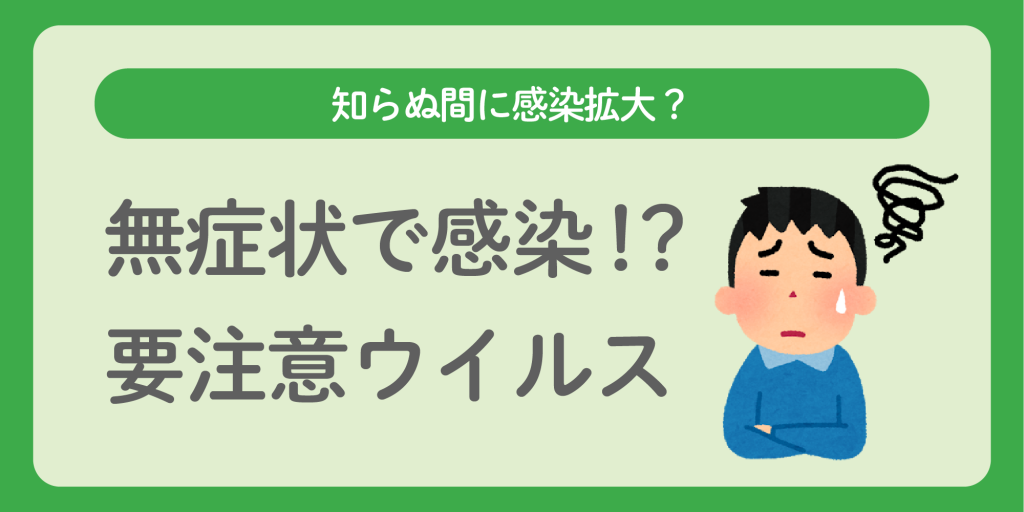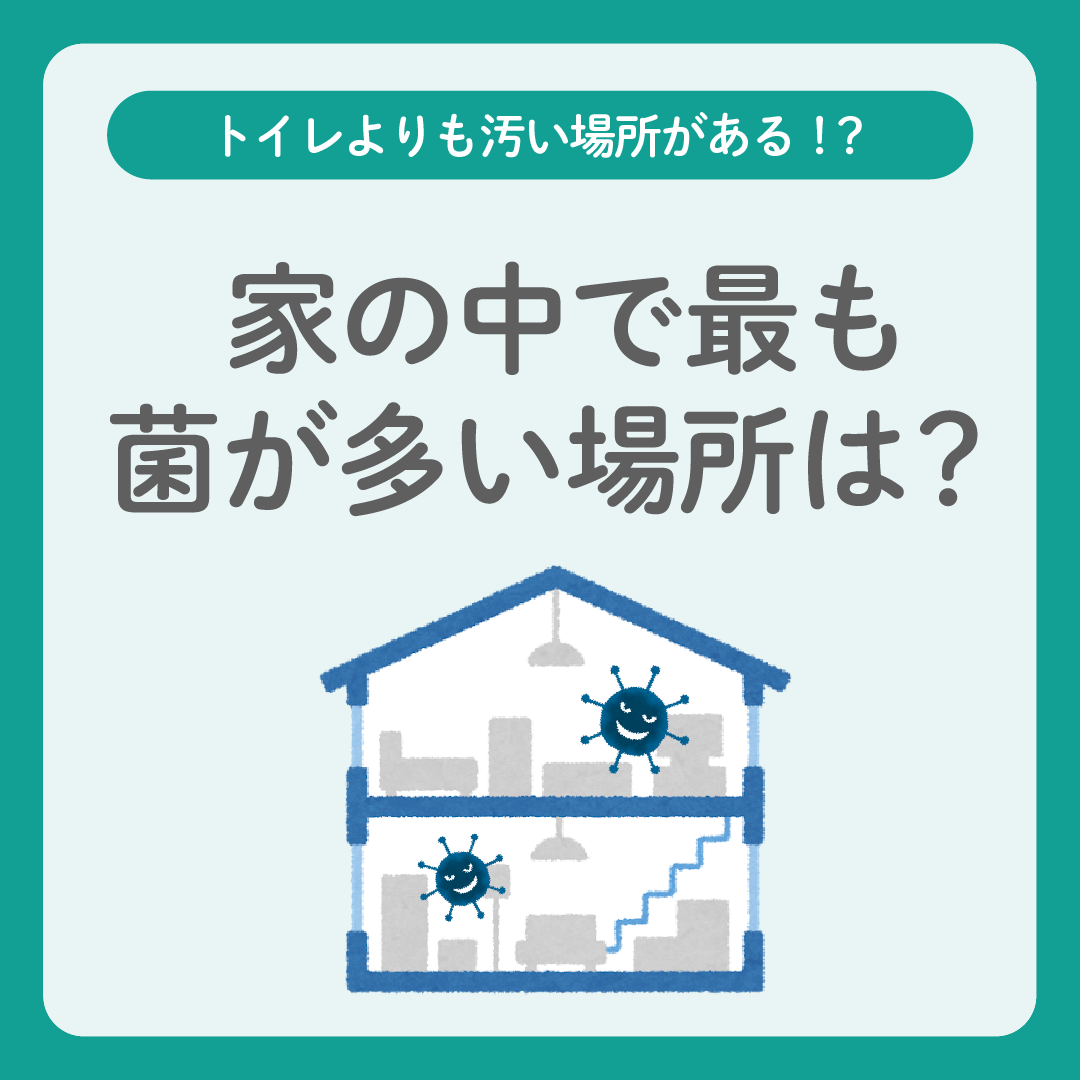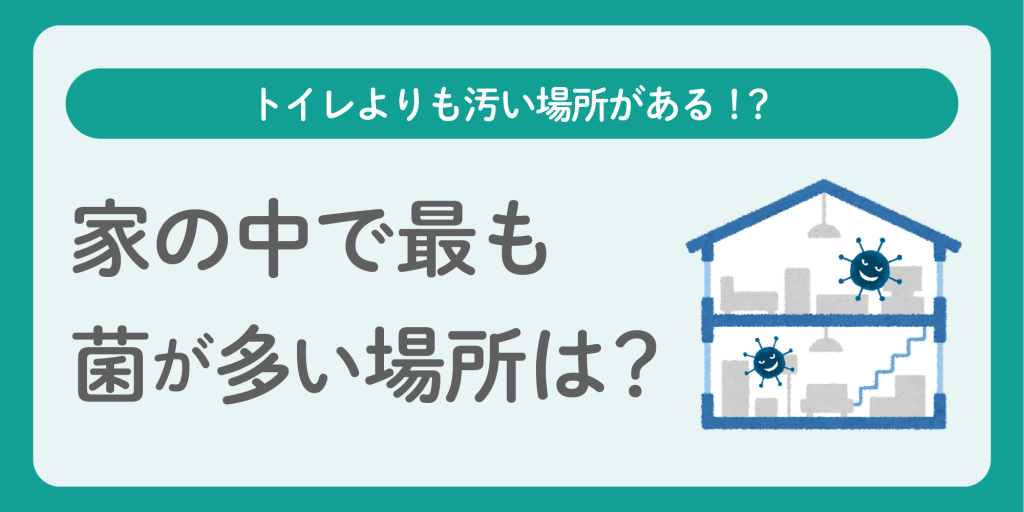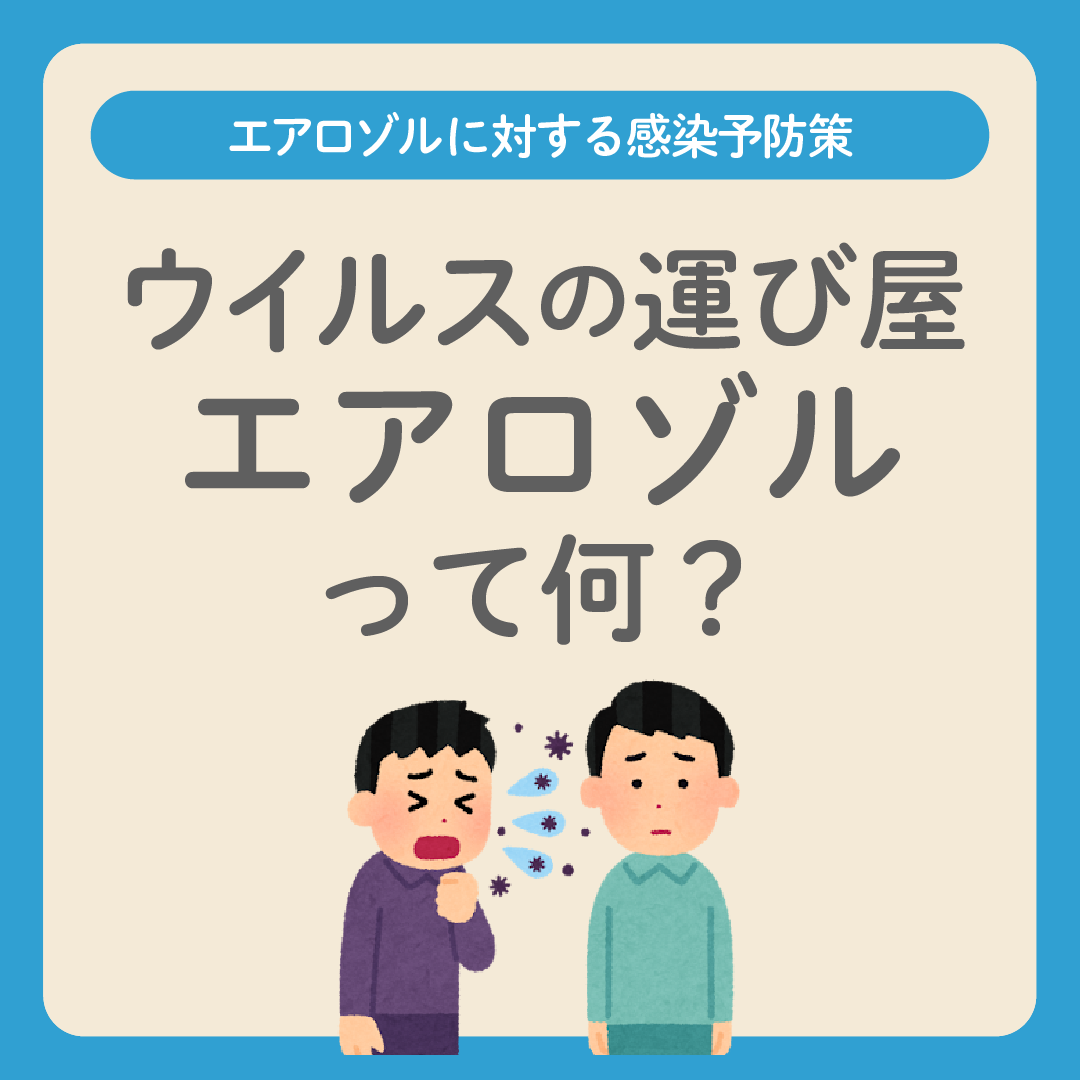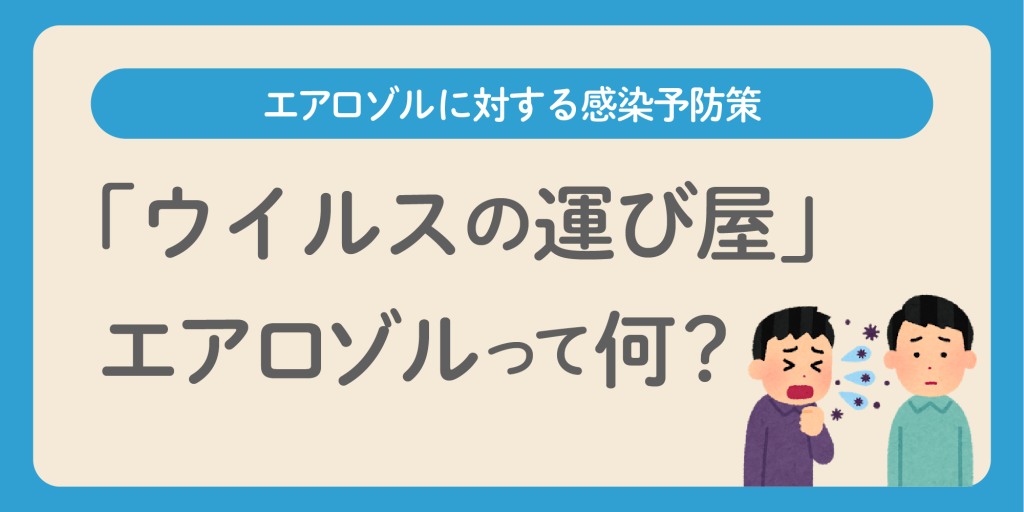スマホから食中毒?ノロウイルスにご用心!
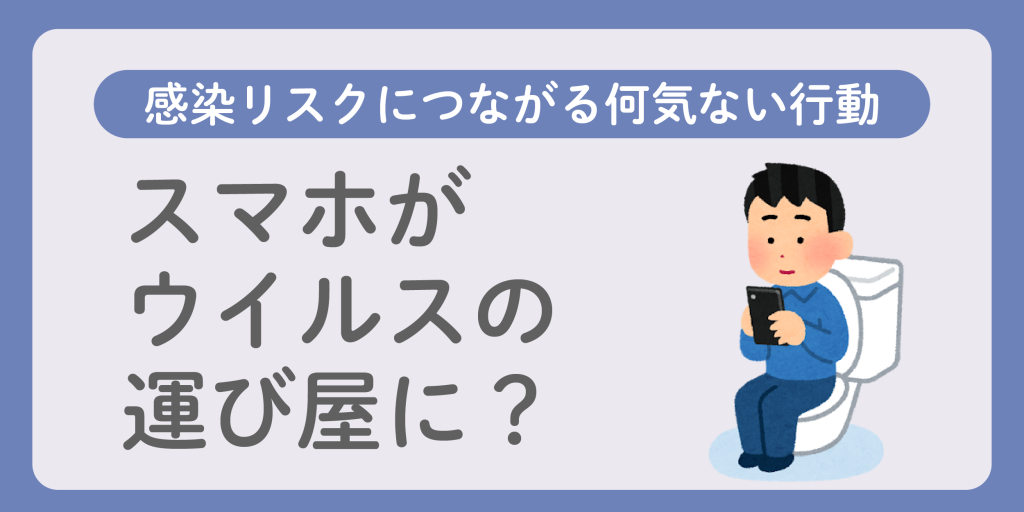
食事中、ついスマホに手が伸びてしまうことはありませんか?
また、トイレの中でもスマホを使ってしまうという人も多いかもしれません。でも実は、こうした何気ない行動が、ノロウイルスのような感染症の原因になることがあるのです。
<スマホがウイルスの運び屋に?>
ノロウイルスは、吐き気や下痢などを引き起こす感染症で、特に乳幼児や高齢者では重症化する恐れがあります。
問題は、スマホの表面にウイルスが付着するリスクです。たとえば、トイレ内でスマホを使用した場合、ウイルスがスマホに付着することがあります。
手を丁寧に洗っても、その後にスマホに触れると、せっかく洗った手に再びウイルスが移ってしまうことに……。
パンやおにぎりなどを手づかみで食べる際には、手の清潔さが何よりも大切。食事中はスマホを触らないよう意識することが、感染リスクを減らす一歩です。
<感染予防の基本をおさらい>
・石けんで丁寧な手洗いを
指の間や爪の周りまでしっかりと洗い、30秒以上の手洗いを心がけましょう。
・食品は十分に加熱
二枚貝などは、中心温度85〜90℃で90秒以上加熱することが推奨されています。
・スマホの取り扱いに注意
トイレでの使用を避ける、食事の前後には触らないなど、少しの心がけで感染予防につながります。
<毎日の「ちょっとした習慣」がカギ!>
ウイルスは目に見えませんが、日々のちょっとした配慮で、感染リスクを大きく減らすことができます。
スマホの使い方や手洗いのタイミングを見直し、健康的な暮らしを守りましょう。