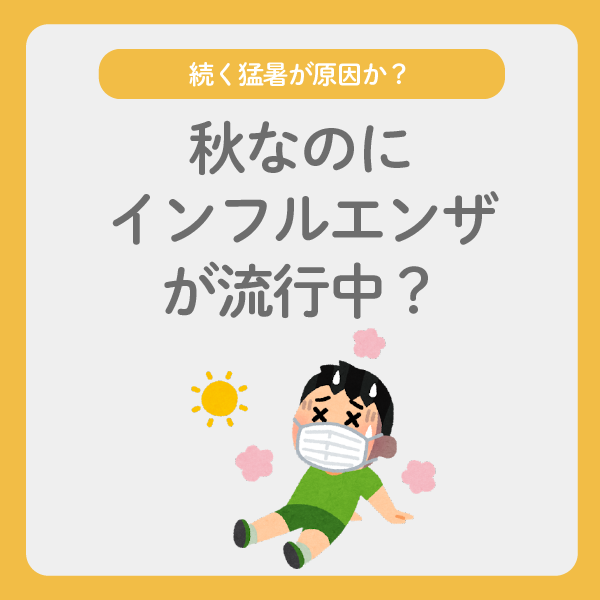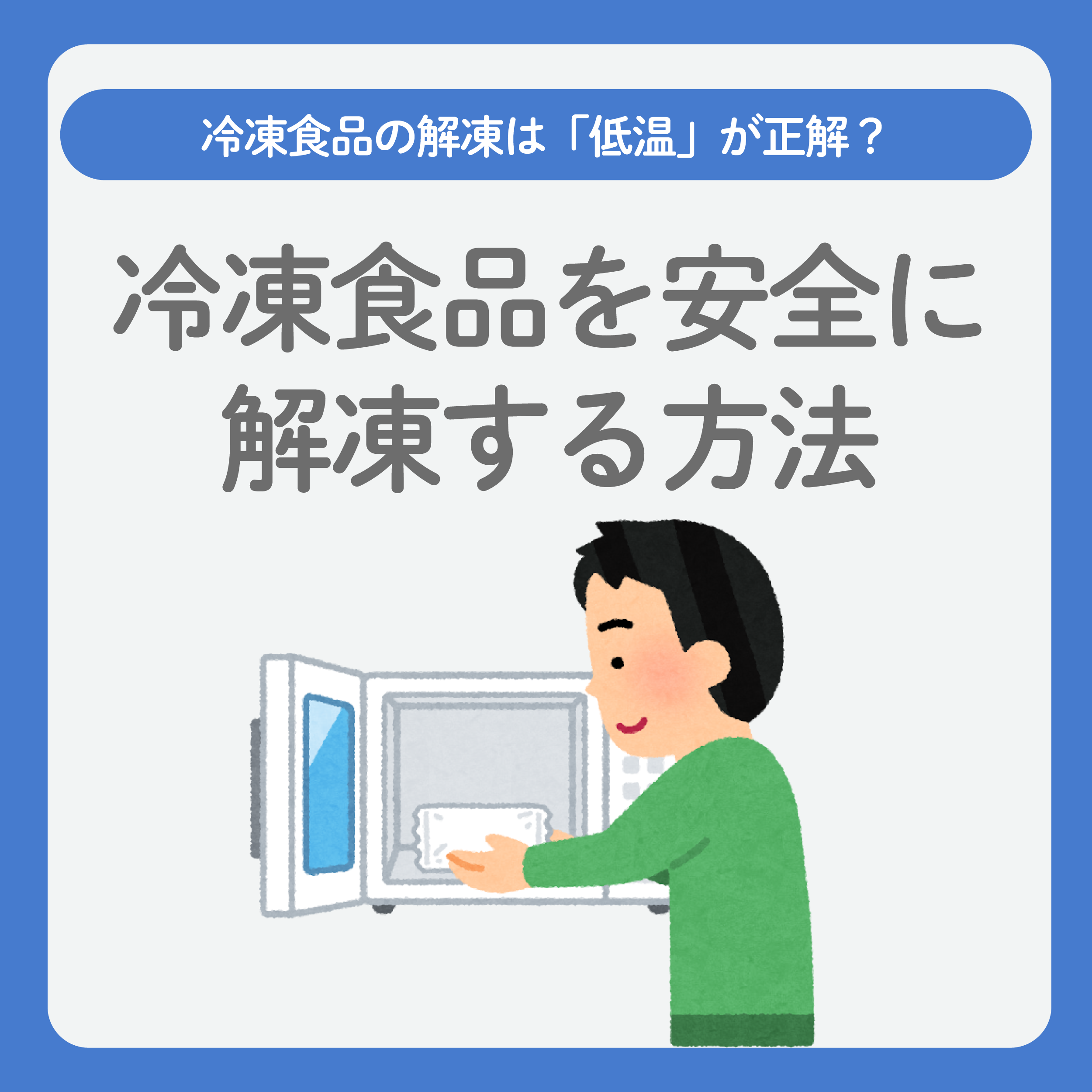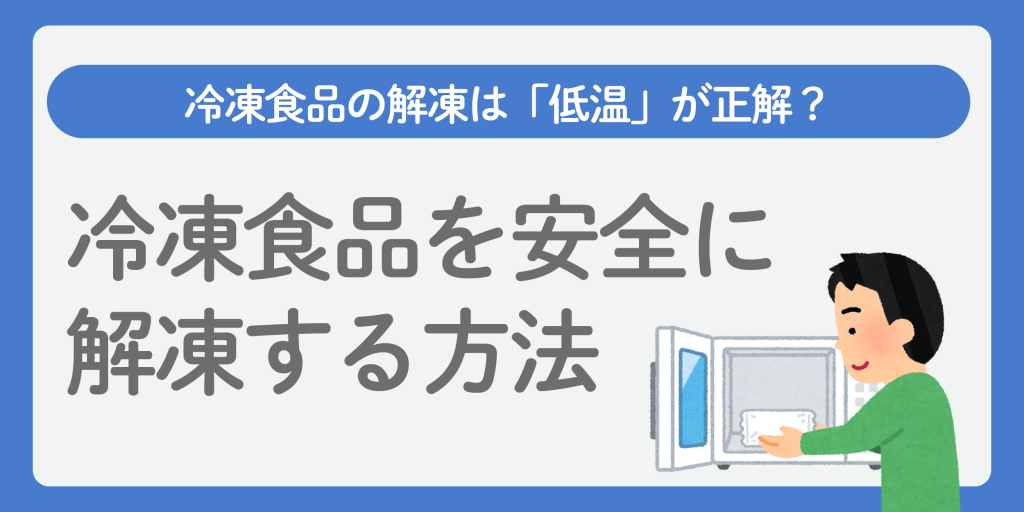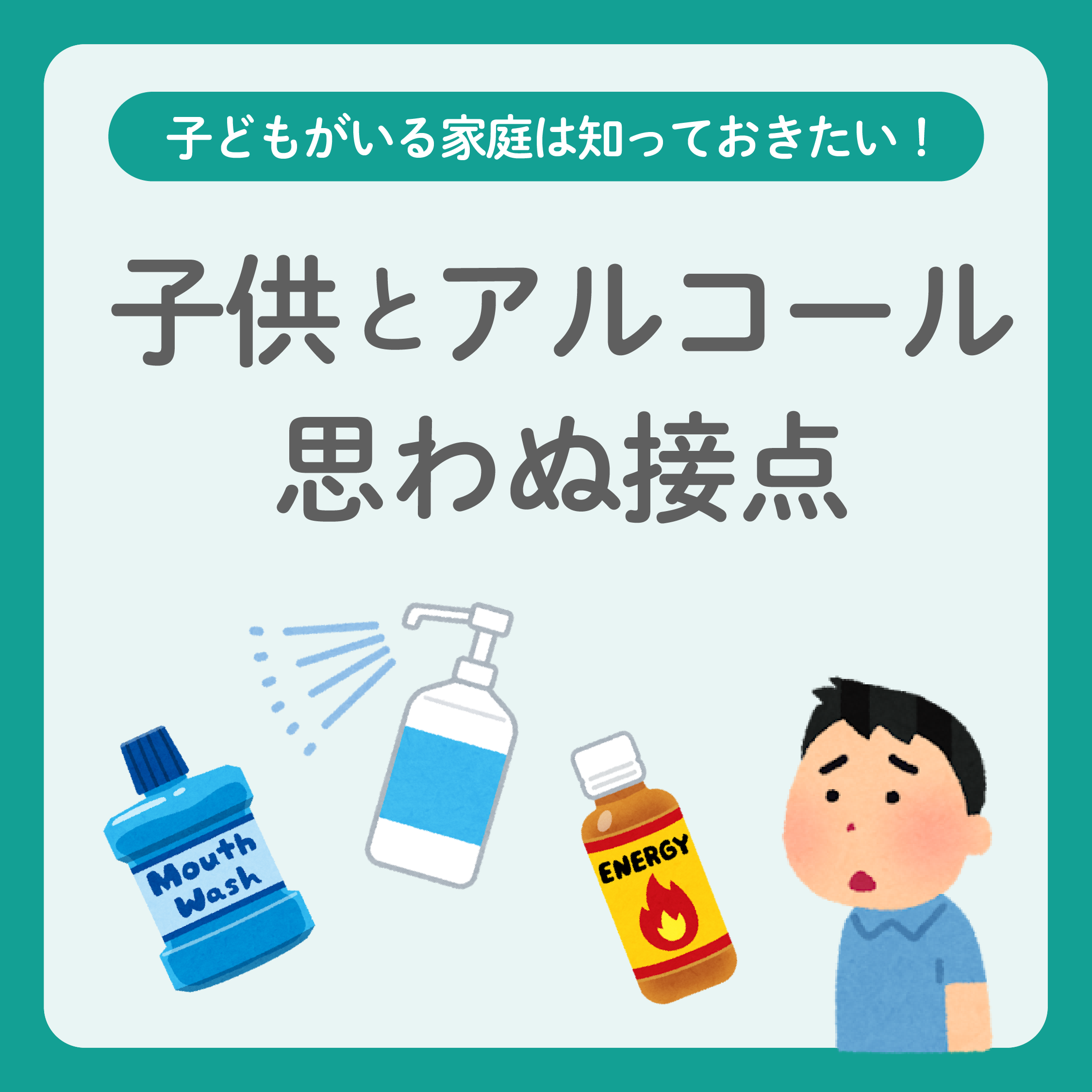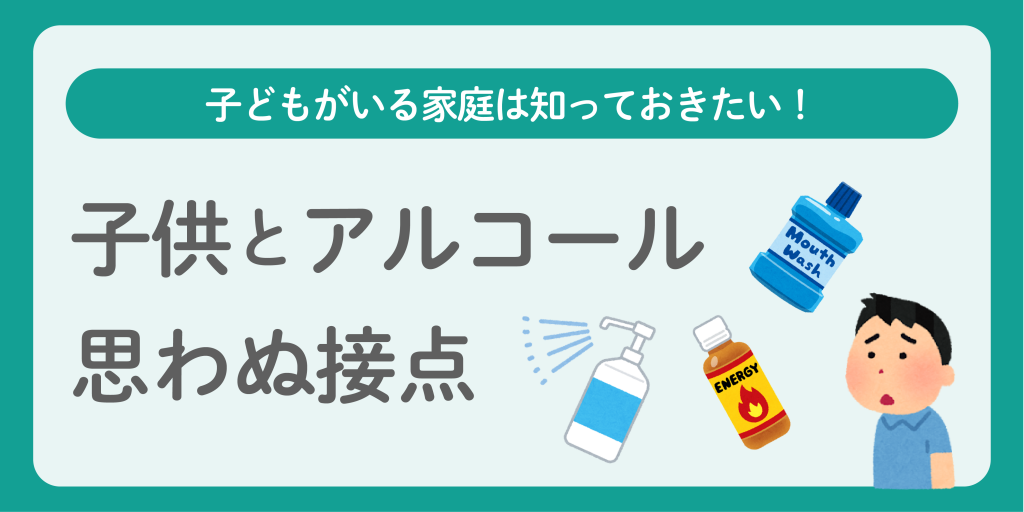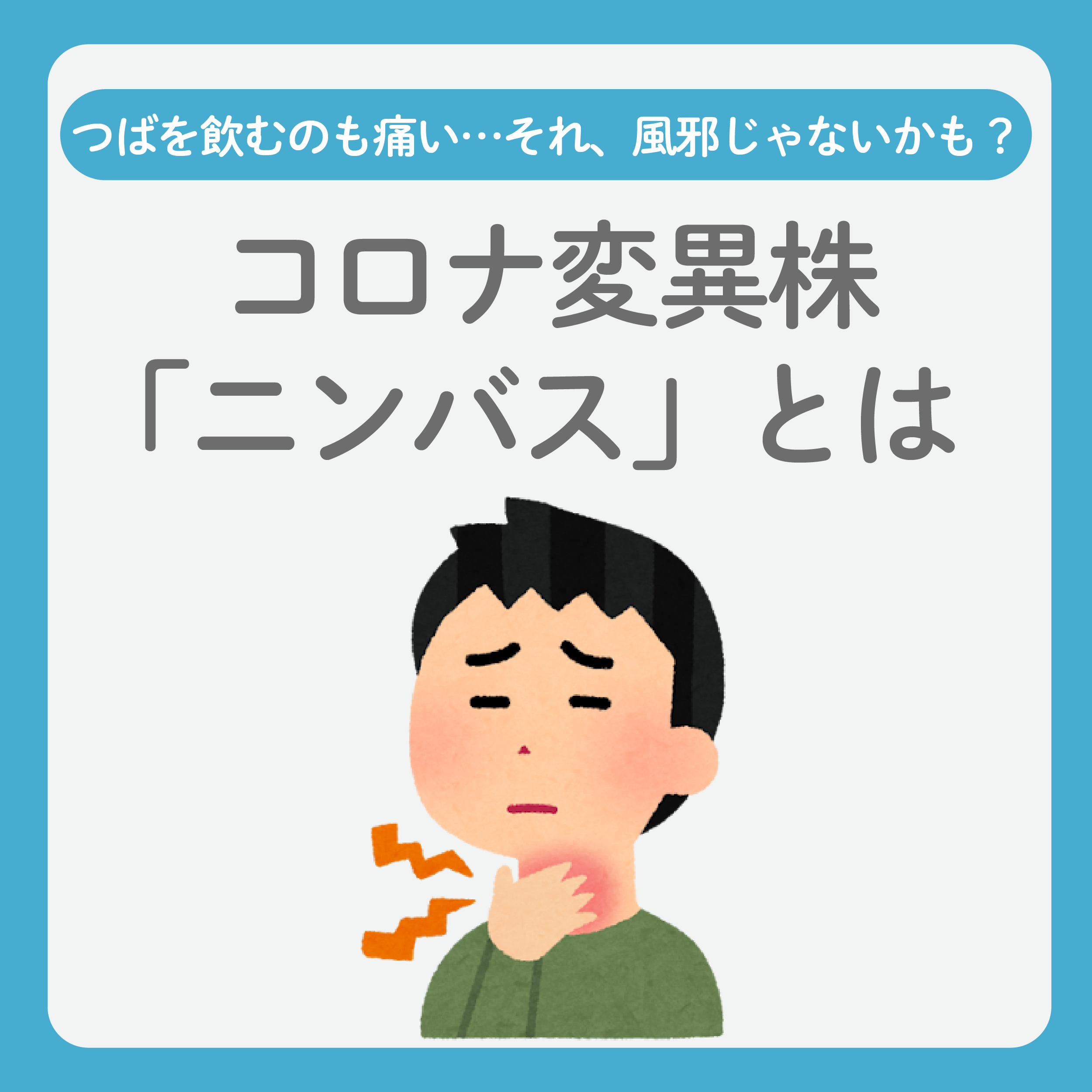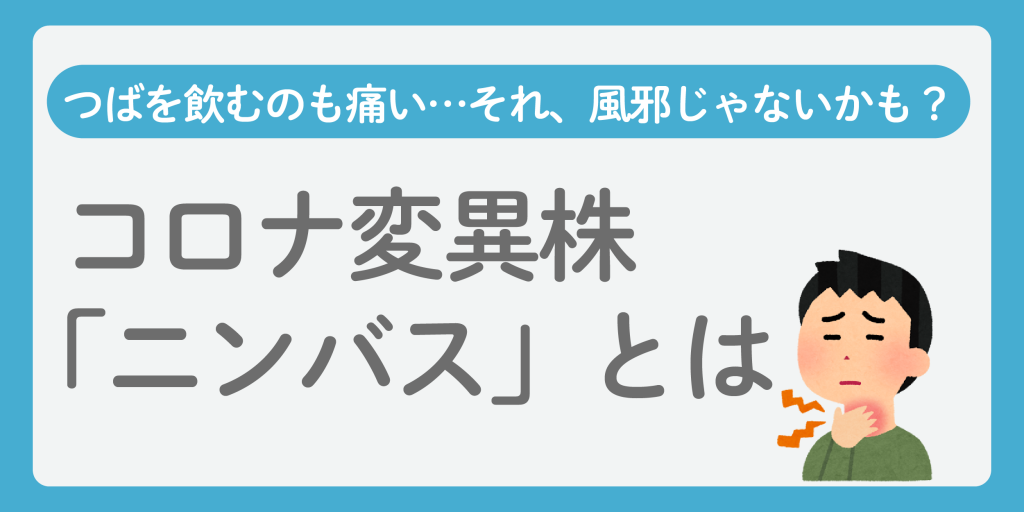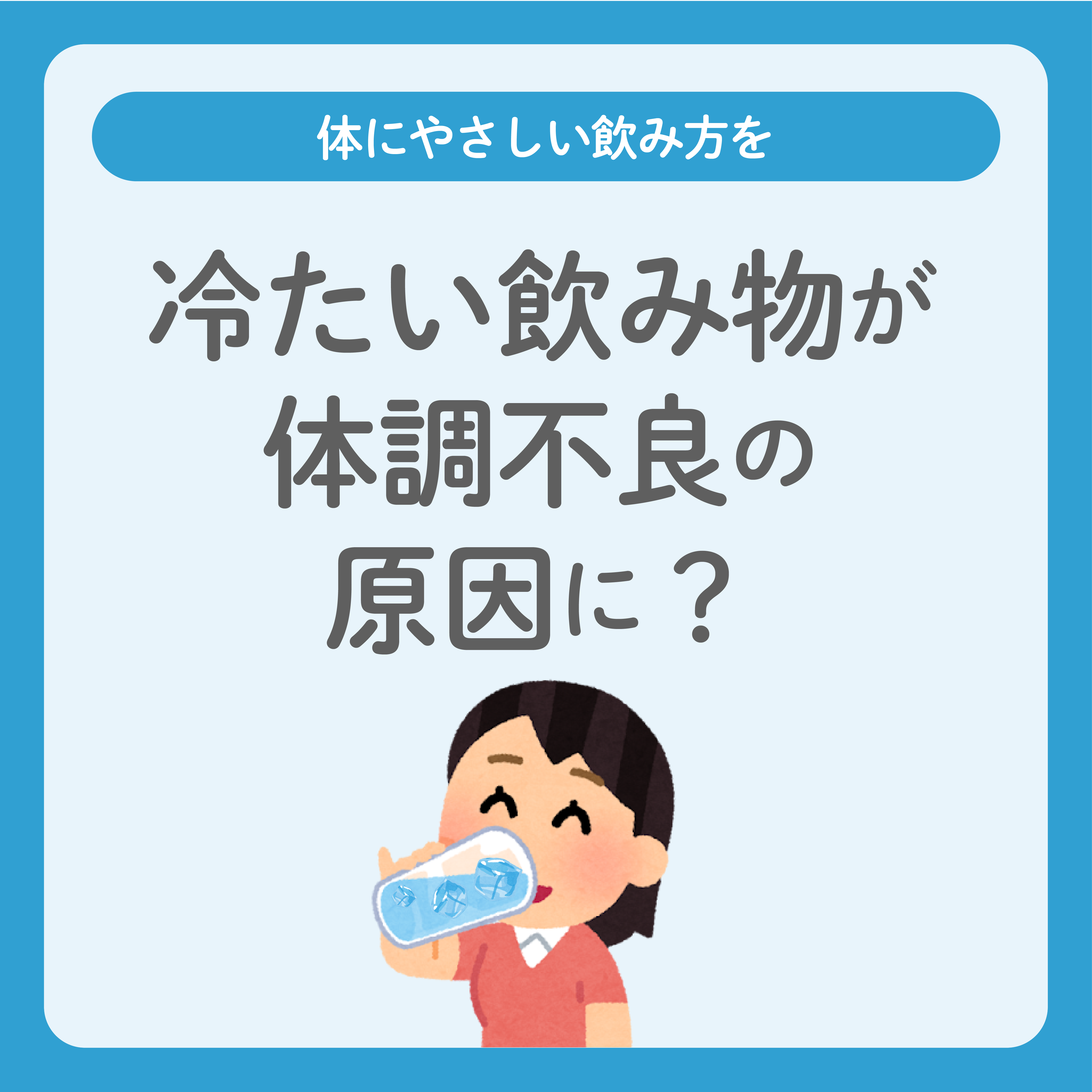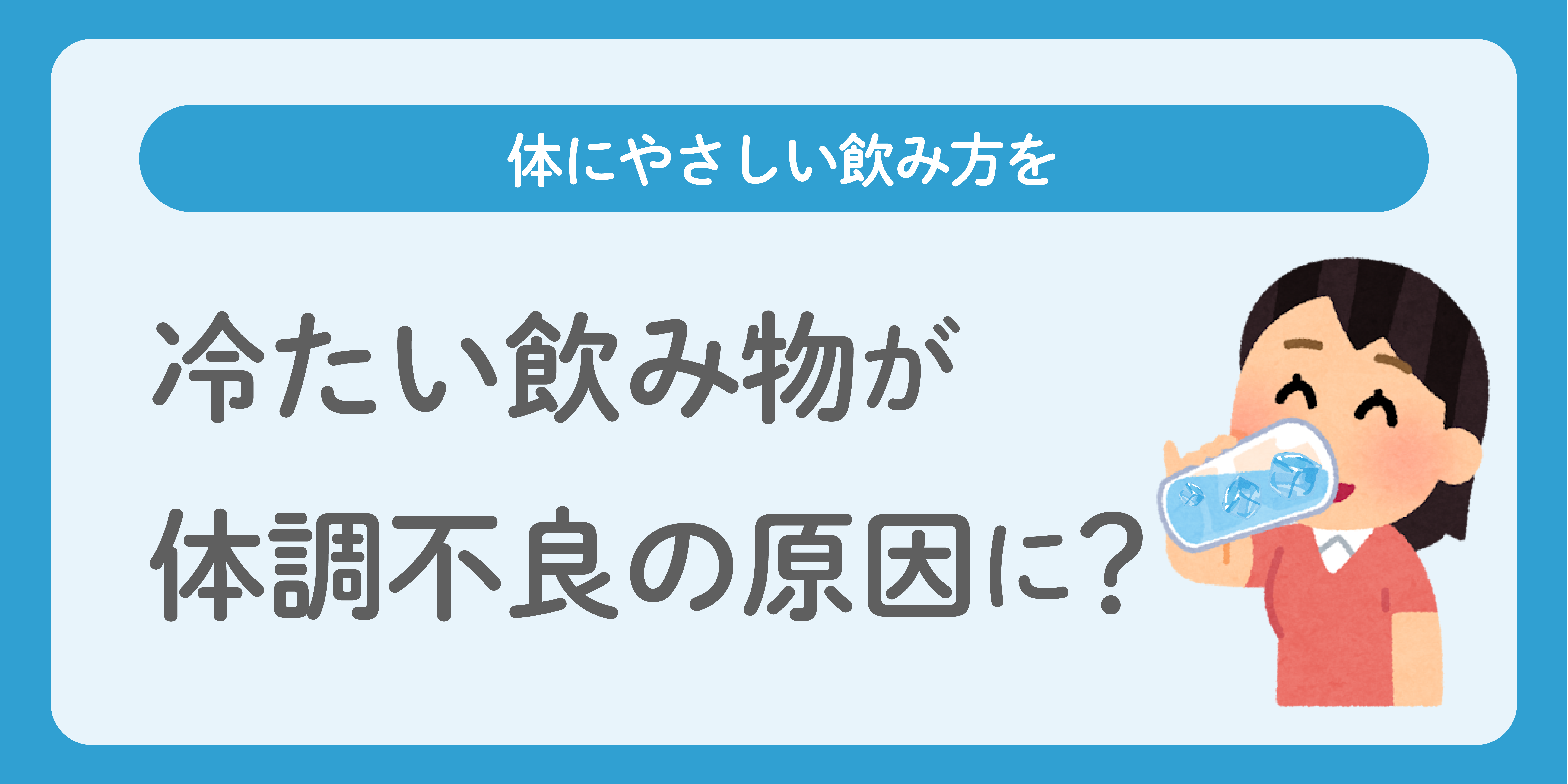秋なのにインフルエンザ流行?猛暑が原因か
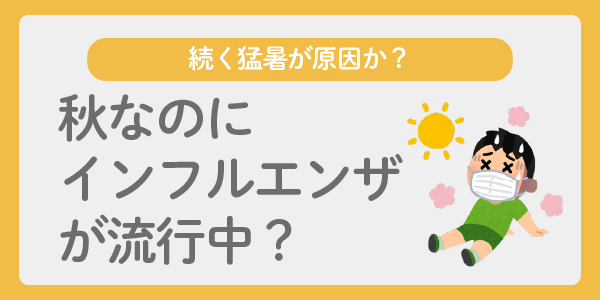
こんにちは、デンネツ広報担当です。
季節外れのインフルエンザが、各地の学校で目立ち始めています。
9月9日から14日の一週間だけでも、全国の小学校・中学校・高校で88クラスが学級閉鎖となりました。これは昨年同時期より33クラス多い数字です。
〈今なぜ広がるのか〉
残暑の影響でエアコンの稼働が長期化。室内の湿度が下がり、ウイルスが拡散しやすくなった可能性があります。さらに暑さのため屋外活動が減り、子ども同士が室内で過ごす時間が増えたことも一因と考えられます。
〈ワクチンはいつ打つ?〉
流行が早めに始まってはいるものの、ピークは例年11月ごろ。ワクチンの効果は個人差はありますが、一般的にはおよそ3か月程度持続するとされています。接種の時期は流行状況に合わせて検討することが大切です。
〈日常でできること〉
・手洗いうがいなどの基本的な予防
・十分な睡眠と休養
・室内の適切な換気
エアコン使用時でも、人の出入りが多い場所や体調不良の人がいる場では、定期的な換気を心がけましょう。
今年はインフルエンザの動きが早い可能性があります。地域の流行情報を確認しながら、日常的な感染対策を続けていきましょう。