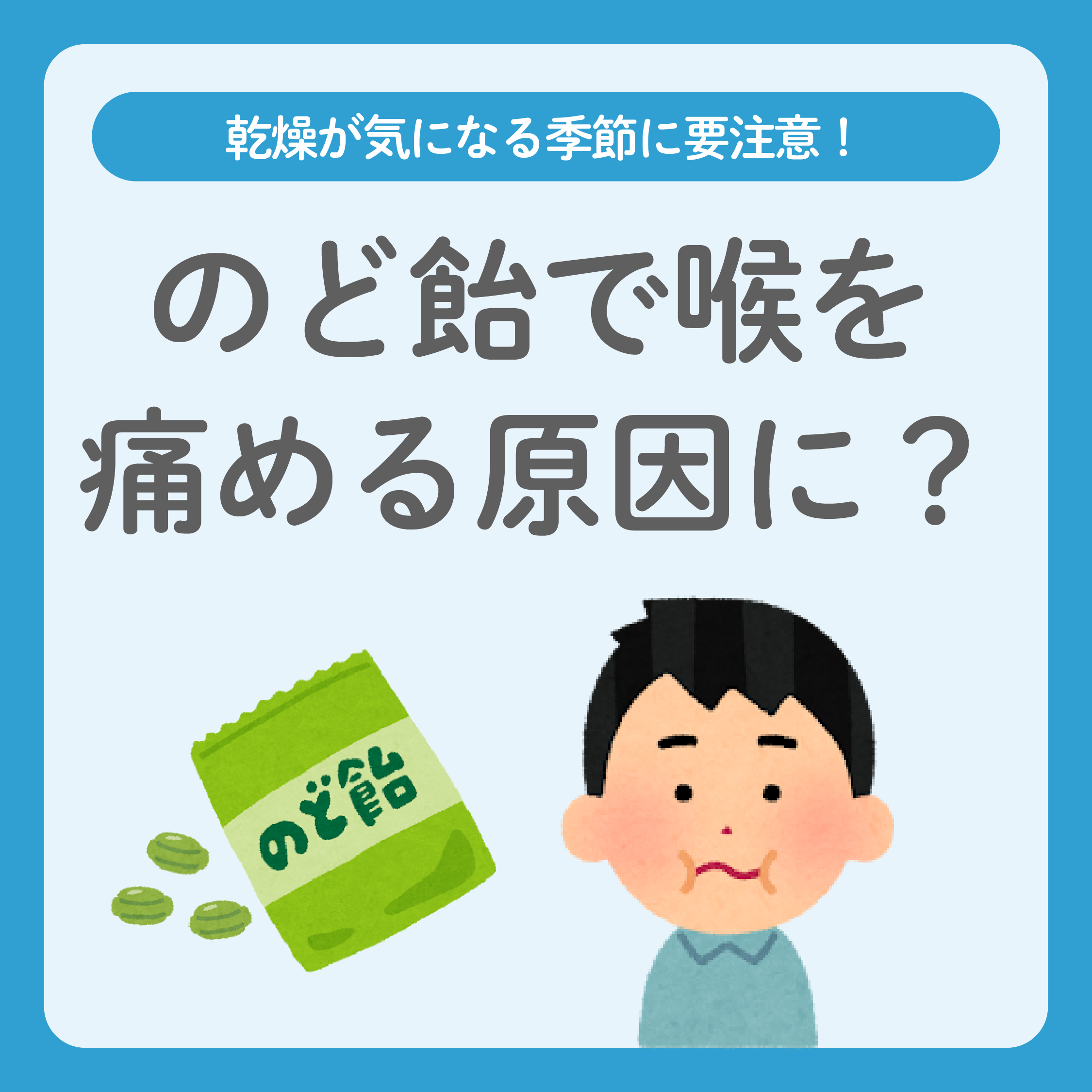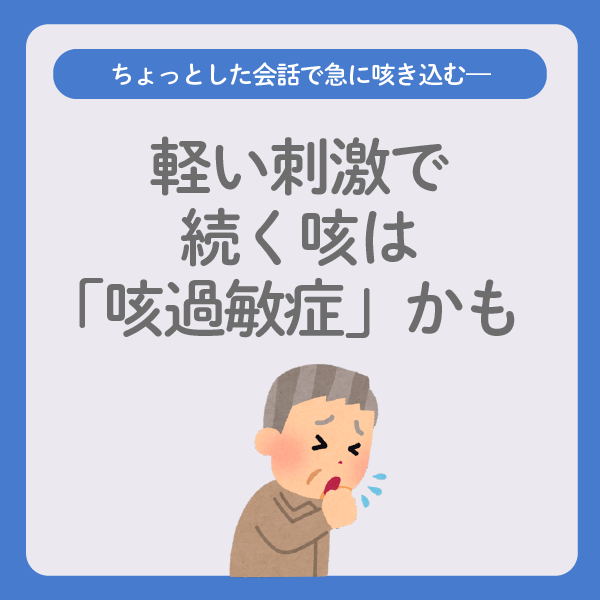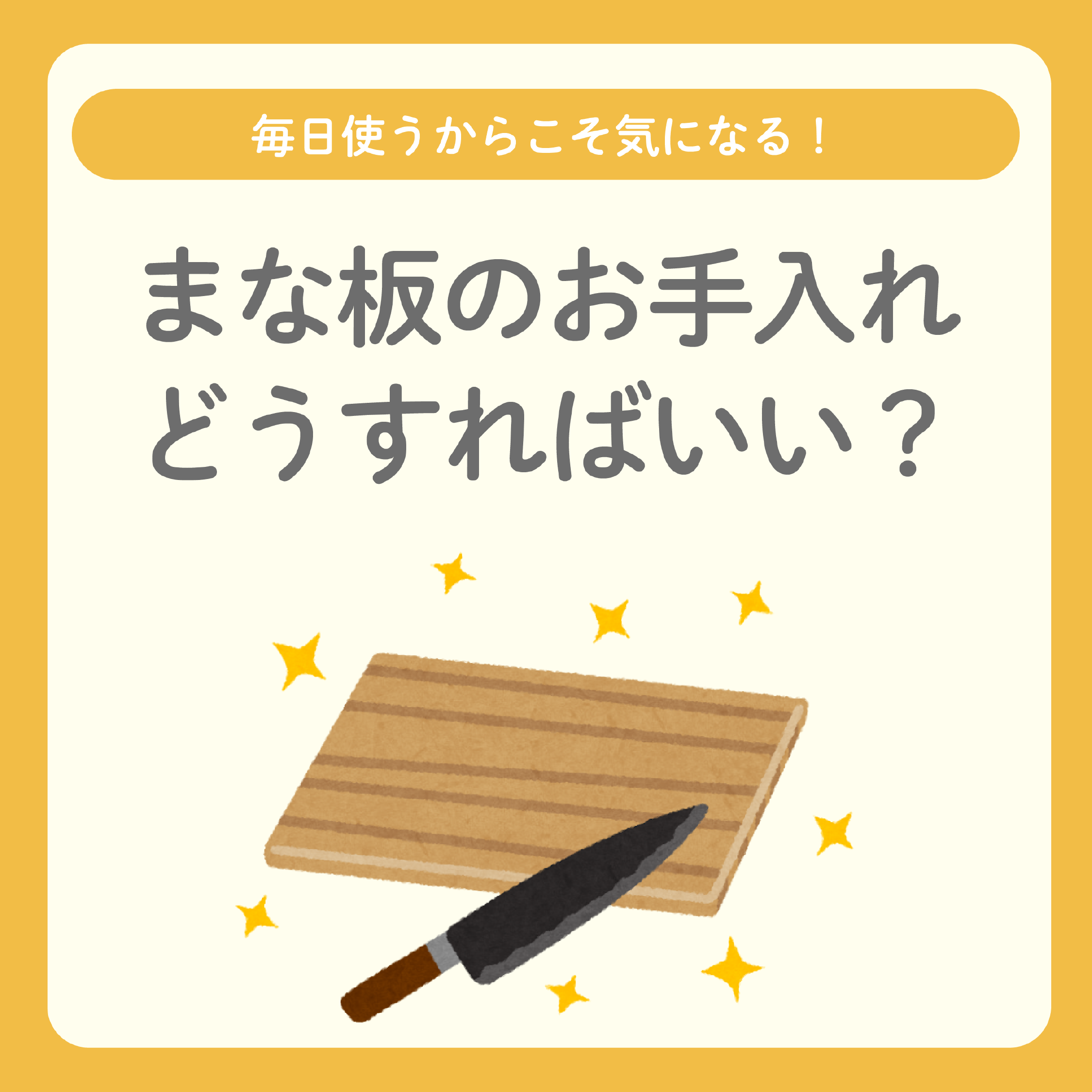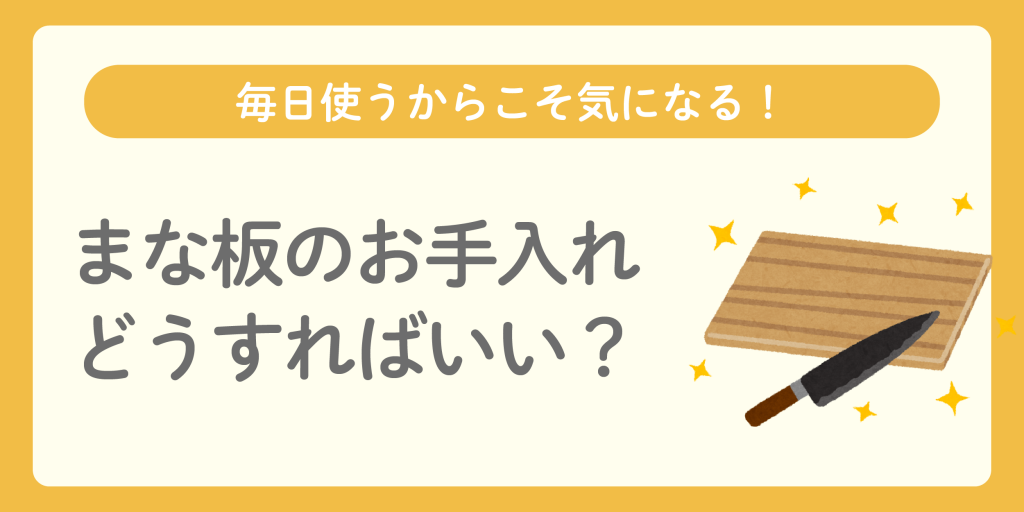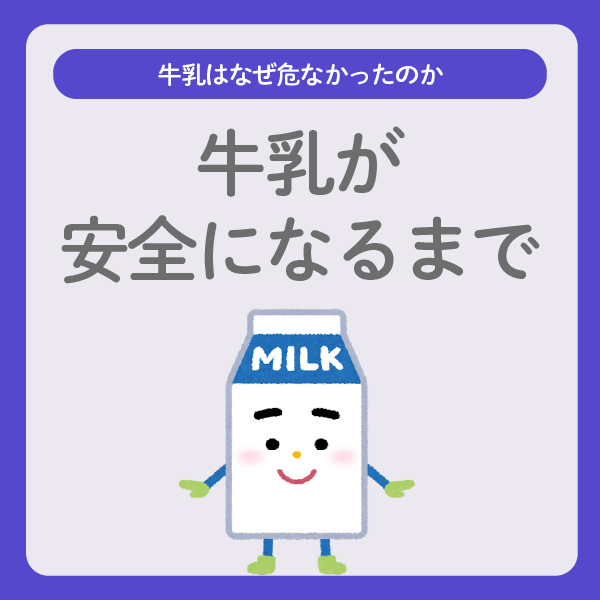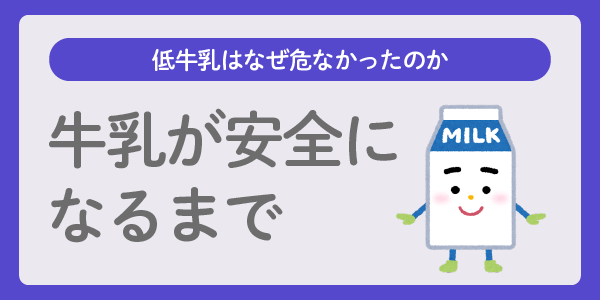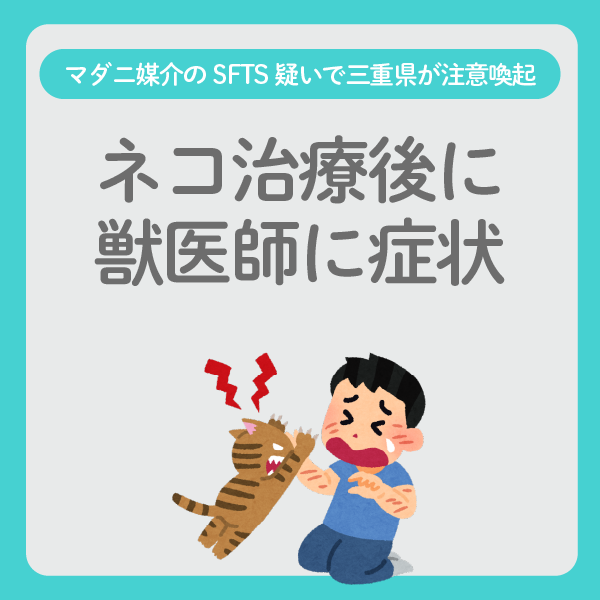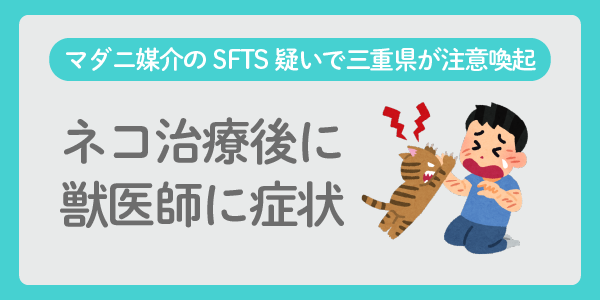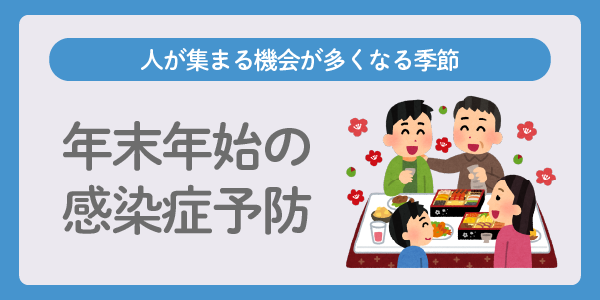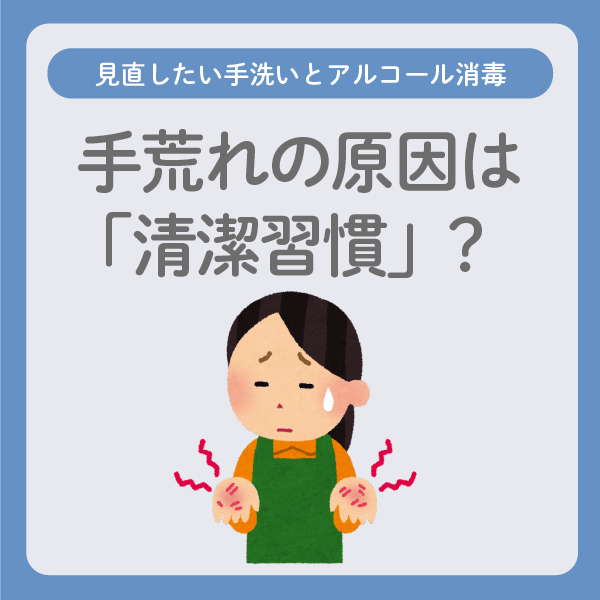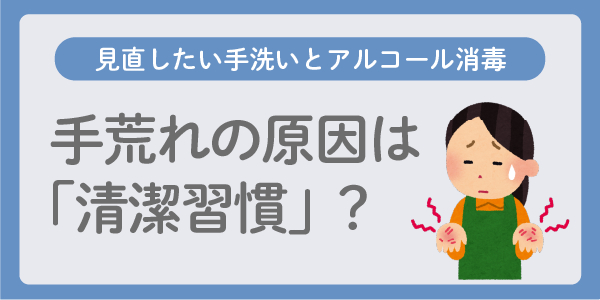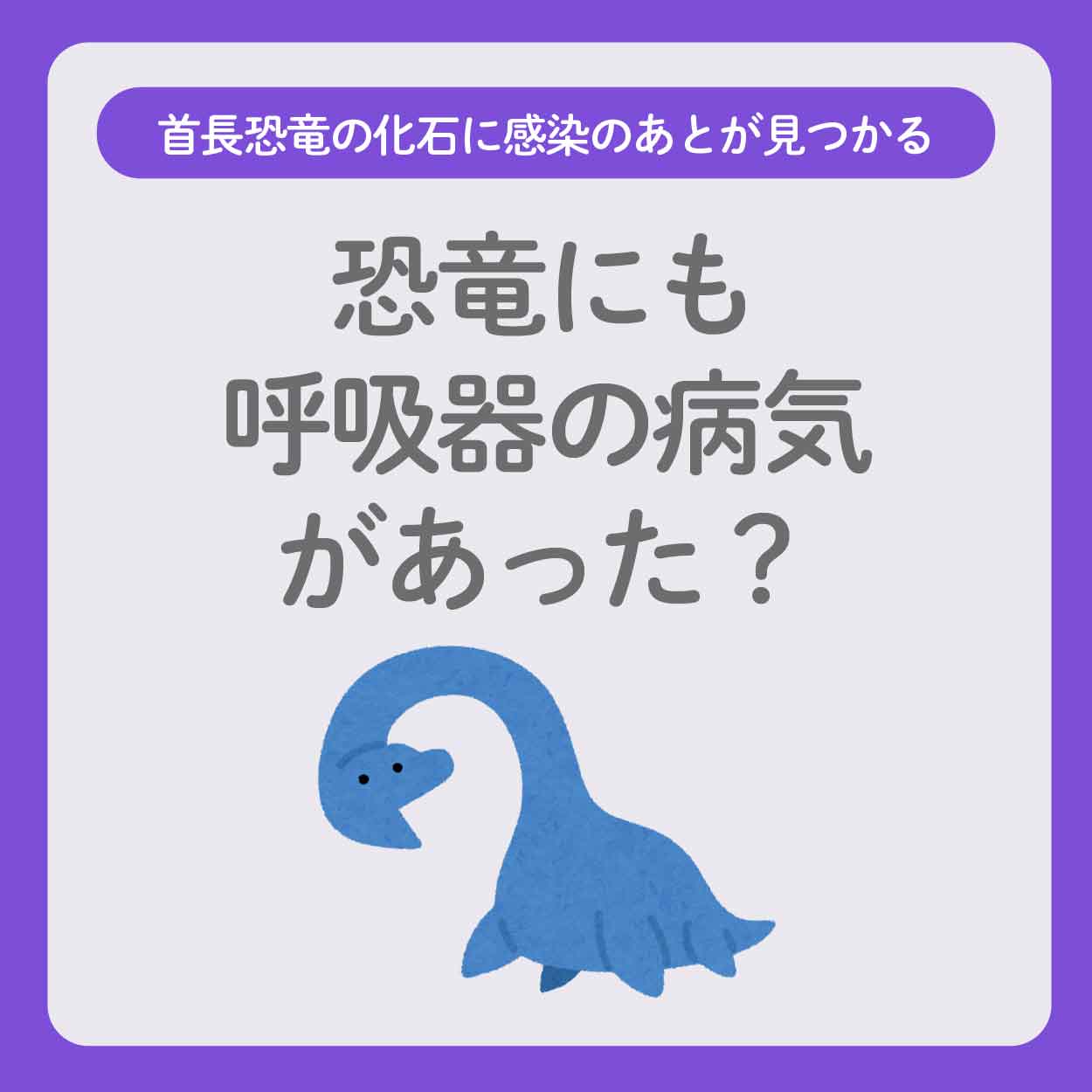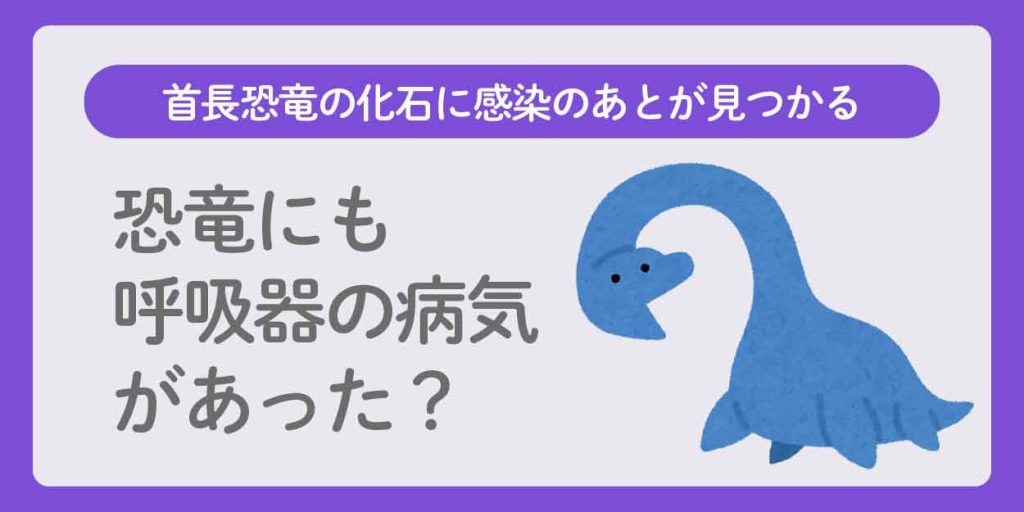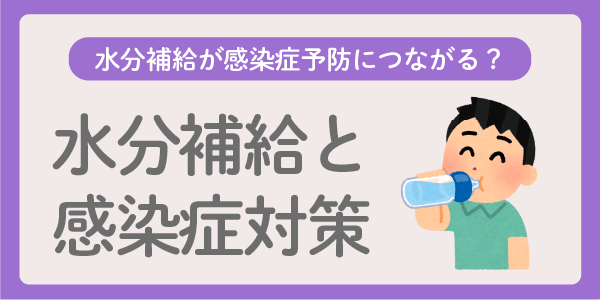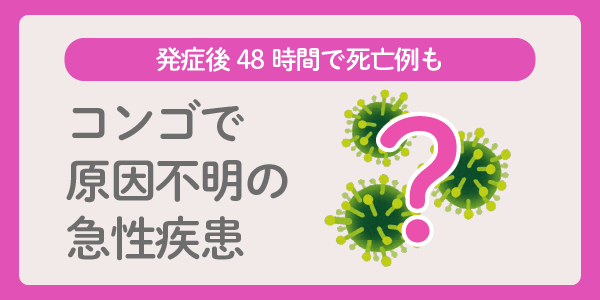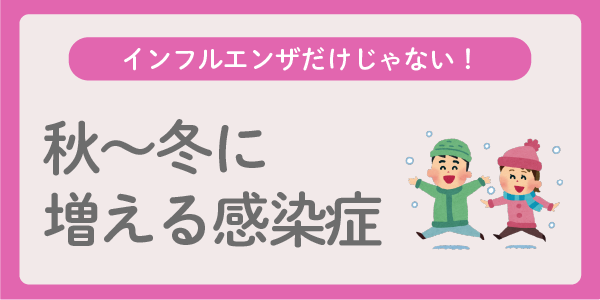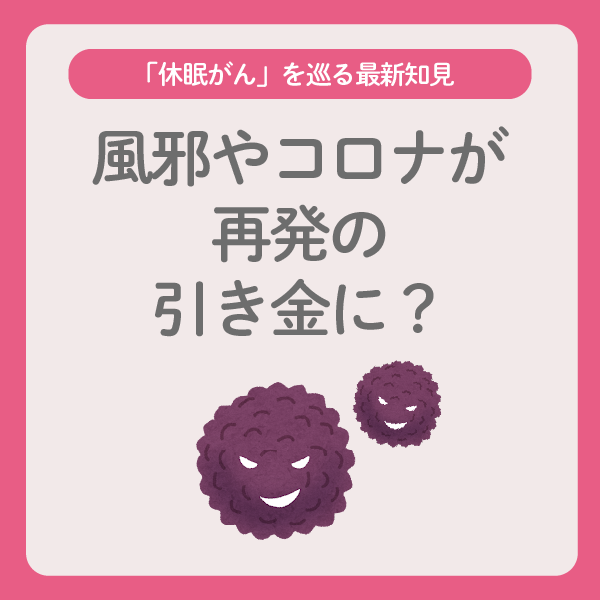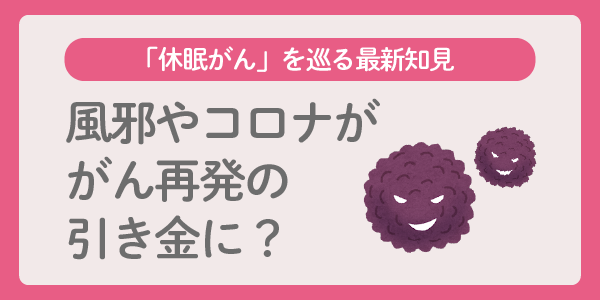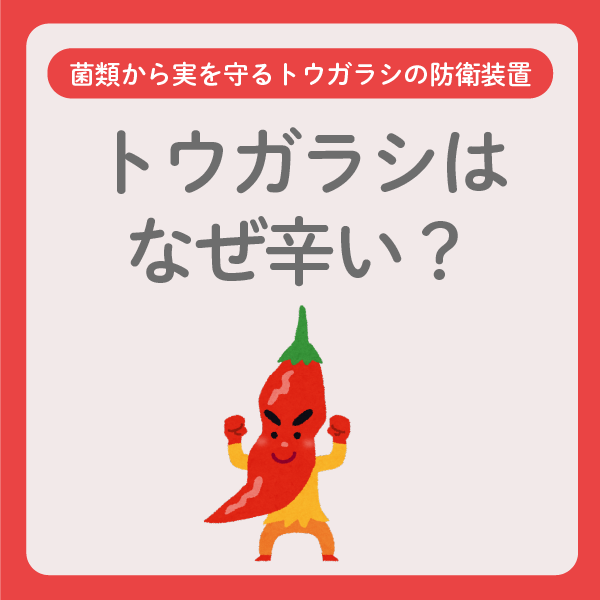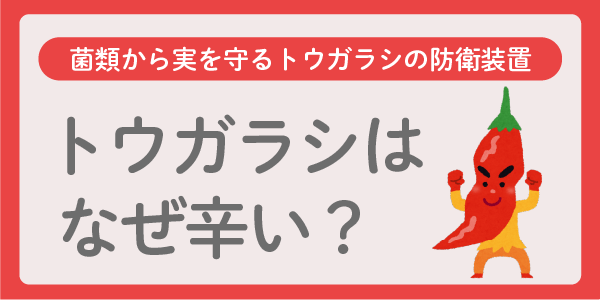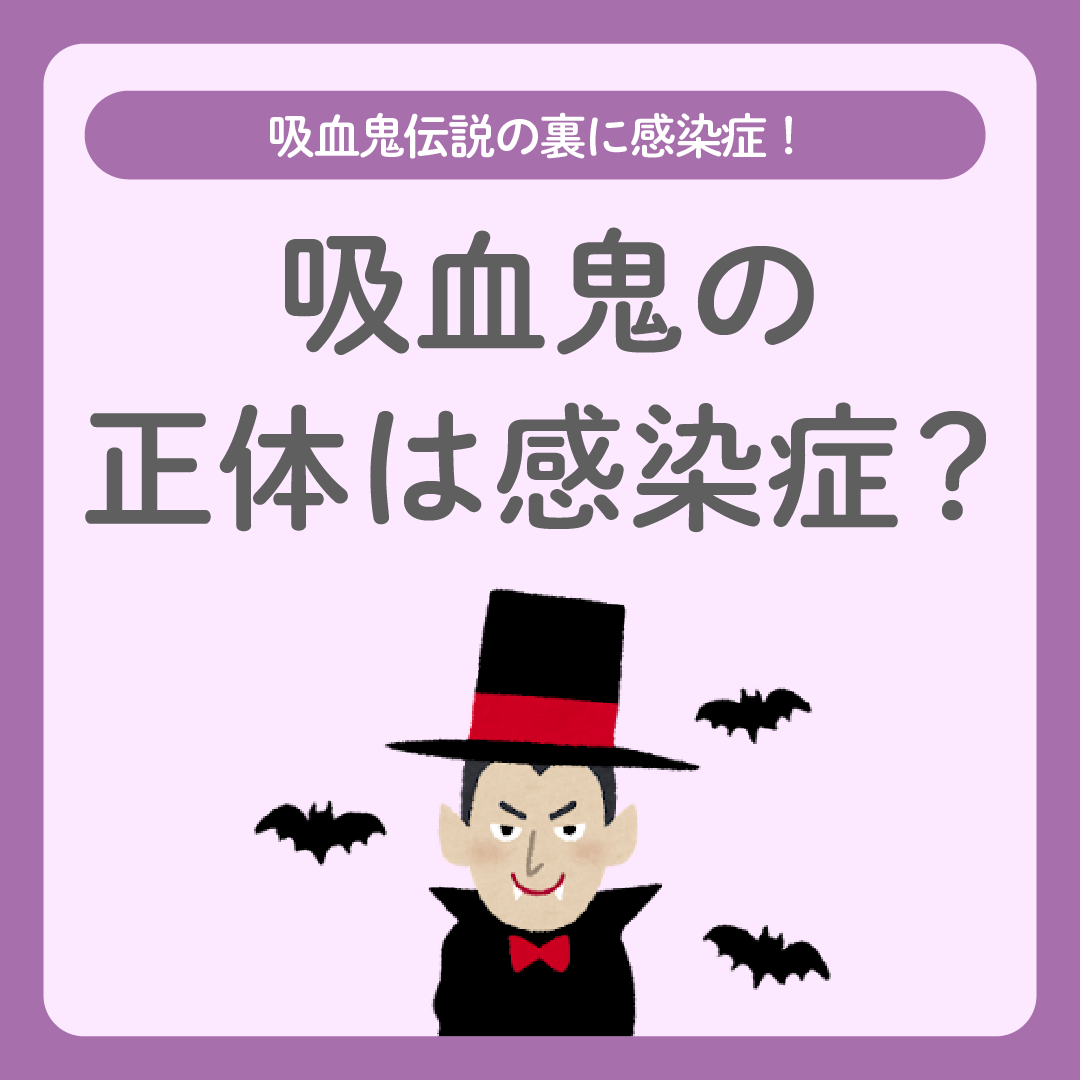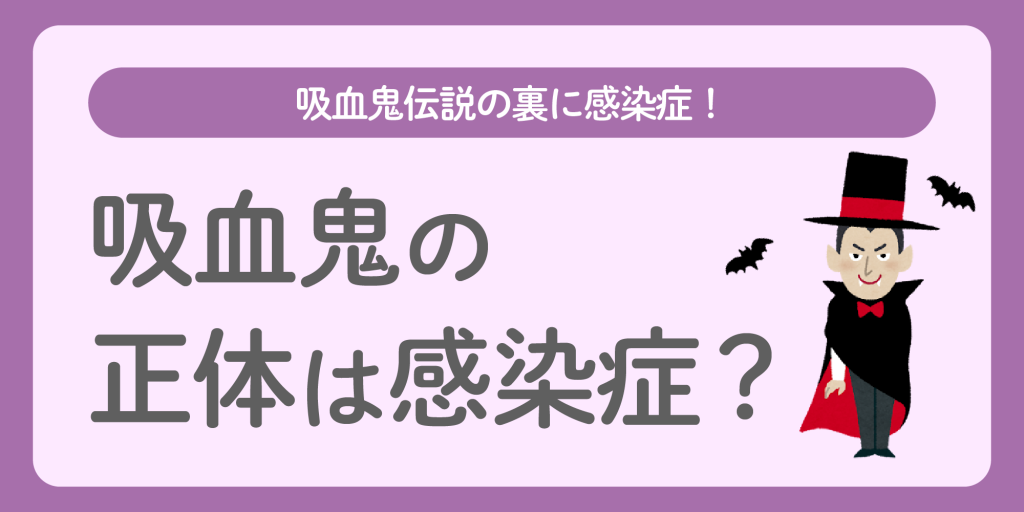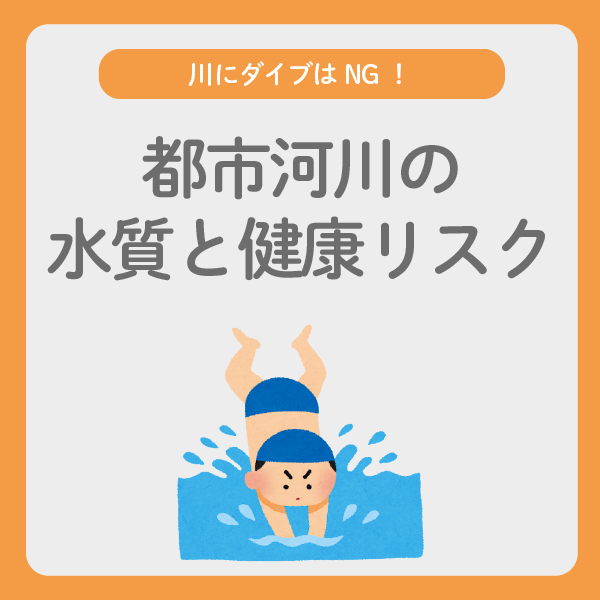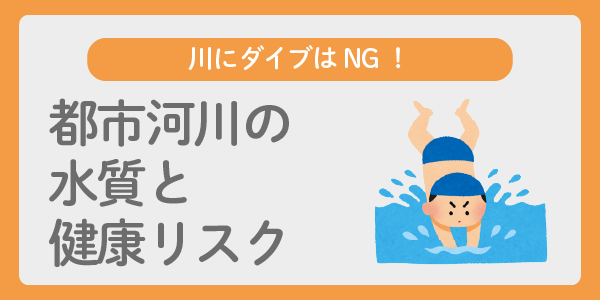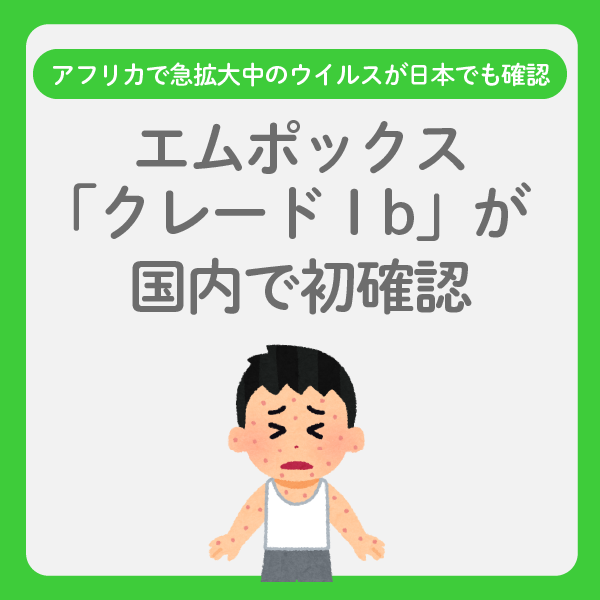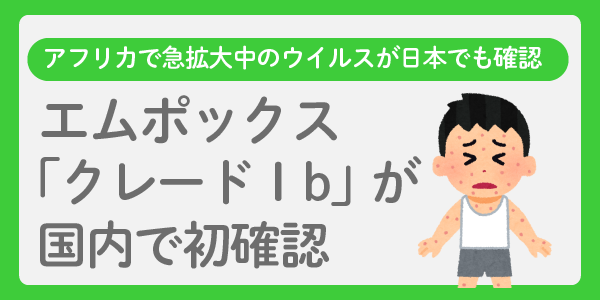のど飴の舐めすぎに注意
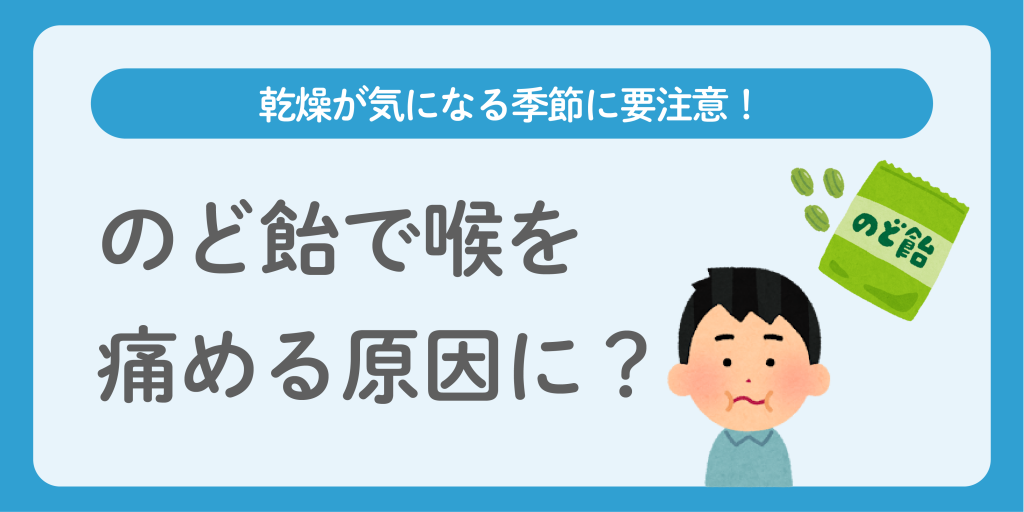
こんにちは、デンネツ広報担当です。
乾燥が気になる日が続いていますね。喉がイガイガしたり、少し痛みを感じると、ついのど飴を口にする方も多いのではないでしょうか。
身近な存在ののど飴ですが、「舐めすぎ」には注意が必要です。
〈喉の自浄作用が低下〉
鼻やのどには、異物や病原体を外へ押し流す仕組みがあります。
唾液はこの働きを助けてくれますが、のど飴をなめ続けていると、唾液が消化に使われやすくなり、粘膜を守る力が弱まることがあります。
その結果、ウイルスや細菌を十分に排除しにくくなり、のどの粘膜も刺激を受けやすくなるため、かえって感染しやすい状態につながるおそれがあります。
〈配合成分による口内・粘膜への刺激〉
医薬品や指定医薬部外品ののど飴には、有効成分が含まれています。そのため、用法・用量を守ることが大切です。
決められた回数を超えてなめ続けると、配合成分が過剰に作用し、舌やのどの粘膜に刺激を与えるおそれがあり、かえって不調を招く可能性もあります。
〈虫歯のリスクが高まる〉
のど飴の多くには砂糖が含まれています。長時間、口の中に飴がある状態が続くと、口腔内が酸性に傾き、虫歯ができやすい環境が続くため注意が必要です。
〈妊娠中の方は特に注意〉
妊娠中はホルモンの影響で体調や口内環境が変化しやすく、虫歯や口内トラブルが起こりやすい時期とされています。
そのため、のど飴をなめる際にも注意が必要です。
特に医薬品ののど飴の中には、妊娠中の使用を推奨していないものもあります。使用前に注意書きを確認し、不安な場合は医師や薬剤師に相談しましょう。
〈のど飴に頼りすぎないために〉
のどの乾燥が気になるときは、まずこまめな水分補給でうるおすことを心がけましょう。
また、加湿器の使用や定期的な換気によって、室内の湿度を適切に保つことも大切です。
のど飴は、軽いのどの違和感があるときに役立つものです。連続してなめ続けるのではなく、間隔をあけて使い、医薬品・医薬部外品の場合は、表示されている使い方を必ず確認しましょう。